「多様性のある森づくり」植林予定地の視察と植林計画の擦り合わせを実施
皆さんこんにちわ。Green Link Lab.(グリーンリンクラボ)スタッフからのお知らせです。
今回は、Green Link Lab.(グリーンリンクラボ)で育てた苗木たちの植林予定地の視察と植林計画の擦り合わせに同行しました。当日は、「森林保全および地域活性化に関する連携協定」を結んでいる、南砺市で林業を手掛ける株式会社島田木材 島田社長、森林保全団体の一般社団法人more trees様、そして、南砺市利賀村を拠点とし地域の森林整備や寺社仏閣屋敷林の整備などを手掛けていらっしゃる一般社団法人moribio森の暮らし研究所様にご案内いただきながら標高約1000mの植林予定地まで登りました。

車で悪路を進み、途中からは道が割れて危険なため、500mほど徒歩で登ります。急斜面で今にも転がってしまいそうな場所ですが、森づくりのプロたちはそんなことはものともせず、まるで平地を歩くかのように進んでいきます。

見晴らしの良いところまで登ってみると、あたり一面伐採された山肌の中に、1本の白樺が目に留まりました。周りに他の木はなく、風雪で横に倒れてもおかしくはないはずなのですが、まっすぐと育っています。

島田社長が、森の循環を守っていこうという思いから、伐採の際に敢えて自生していた木々は残していたそうです。作業効率を考えると、すべて伐採してしまったほうが負担は少ないのですが、森を尊重する想いから一貫した理念で作業にあたっていることが伝わってきました。
あたりを観察しながら、エリアごとに区切って、天然更新エリア、掻き起こしエリア、植林エリアに分類していきます。
・天然更新エリア…前生/後生稚樹の数が多く、現状のまま天然更新が期待できる。
・搔き起こしエリア…母樹が近くにあり、追加作業によって天然更新が期待できる。
・植林エリア…天然更新だけでは成林が難しい。
この分類を決定するために、皆で森の急斜面の中に入って行ってどの程度自生していた樹々の苗木があるかを調査します。また。土壌の渇きや水脈、風向き、ちょっとした標高差による気温の変化も加味し植林すべき樹種の判断をしていくため、プロたちで様々な知見を持ち寄って話し合いがなされました。

どの樹種をどのエリアに植えていくかは、樹種ごとの特性、たとえば乾燥に強いか、耐陰性が高いか、高木なのか、低木なのかなどを考慮する必要があります。
多様性のある森づくりでは、植林といってもただ植えていけばいいのではなく、適切なゾーニングをすることで自生林に近い森を目指していくのです。

今回視察した場所だけでも膨大な広さがあり、ここに森を再生していくためには数十種類、数千本単位の苗木が必要になります。
多様性のある森づくりの課題のひとつは、地域に自生している多種多様な広葉樹の苗木が足りないということです。国をあげて多様性のある森づくりが推進されているなか、Green Link Lab.(グリーンリンクラボ)で苗木を育てるということが、どれだけ社会意義の高いことなのかということを再認識させられました。
また、森づくりには様々な想いをもったプロフェッショナルが関わっており、このチームの中にGreen Link Lab.(グリーンリンクラボ)が携われることは、障がいを持つかたにとって、社会参画の大きな一歩だと感じました。
Green Link Lab.では障がいを持つ方々の多様な生き方を実現するための手段として、多様性のある森づくりに必要不可欠な、多種多様な広葉樹の苗木生産にチャレンジしています。
ラボで大切に育てられた苗木は山に植えられ、長い年月を経て立派な森へと成長していきます。
私たちは個性豊かな人材や苗木の成長を支援し、100年先の未来につなぐ社会インフラとなることを目指しています。

■本件に関するお問合せ
会社名:株式会社ミチルワグループ 新規事業推進部
所在地:東京都中央区東日本橋3丁目3−7 近江会館ビル3F
Tel:03- 3527-3837
Mail:info@greenlinklab.jp
URL: https://greenlinklab.jp/
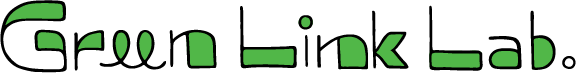
 無料オンライン相談
無料オンライン相談
