【専門家による解説!】障がい者雇用支援サービス・支援機関の選び方は?
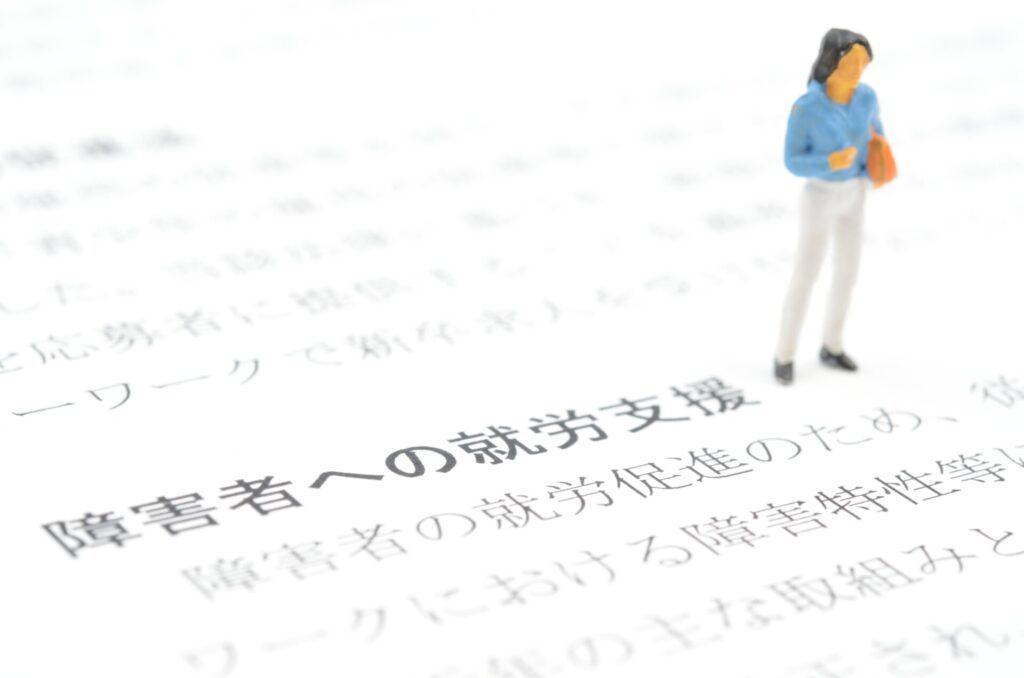
障がい者雇用を進めるには、障がい者雇用支援サービスや支援機関の利用がおすすめです。
求人票の作成方法や必要な設備の提案、業務の割り当て、採用後の定着支援など幅広くサポートしてもらえるため、障がい者雇用について知見がない企業でもスムーズに進められます。
しかし、障がい者雇用支援サービスや支援機関を利用したことがない方は「どれを選べばいいのかわからない」という悩みもあるでしょう。
当記事では、障がい者雇用支援サービスや支援機関の選び方について詳しく解説します。
各サービスの種類や特徴についても説明するので、ぜひ参考にご覧ください。
目次
障がい者雇用支援サービスとは
障がい者雇用支援サービスとは、障がい者雇用を求める企業に向けた支援を行うサービスのことです。民間企業は一定以上の従業員を雇用している場合、障害者雇用率制度の法定雇用率に基づいて障がい者雇用を進めなければいけません。
法定雇用率は年々引き上げられる傾向にあり、民間企業の障がい者雇用は拡大されています。
障がい者雇用支援サービスでは、障がい者雇用に関する課題に合わせて人材紹介や定着支援、研修・セミナーなどのサポートを提供可能です。
障がい者雇用支援サービスは、主に以下のような種類に分類されています。
| 種類 | 特徴 |
| 雇用コンサルティングタイプ | 障がい者の採用〜定着までコンサルティングがサポート |
| BPOタイプ | 主に企業から切り分けた業務を対応 ・常駐スタッフのサポート ・障がい者の管理対応など |
| 人材紹介タイプ | 希望条件に合った障がい者の人材紹介 |
| 農園型 | 運営会社から借り受けた農園で障がい者を雇用 |
企業の求める環境に合わせた支援方法を選択することで、障がい者の採用活動をスムーズに進めることが可能です。
総合的なサービスを提供している企業もあるので、状況に合った障がい者雇用支援サービスを選択することをおすすめします。
障がい者雇用の支援機関とは
障がい者雇用の支援機関とは、国や自治体などが提供している障がい者雇用向けの機関です。
障がい者雇用の促進を目的としており、無償で民間企業の採用活動を支援しています。
全国に設置されている支援機関も多いため、地域を選ばず利用可能です。
それでは次項から、障がい者雇用の支援機関の種類について説明します。
支援機関の種類
障がい者雇用の支援機関には、以下のような種類があります。
- ハローワーク
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
- 就労定着支援事業所
- 特別支援学校
それでは各支援機関の特徴について、詳しく説明します。
ハローワーク
ハローワークは、仕事を探している求職者や求人事業主に対して幅広い雇用サービスを無償提供しています。民間企業の障がい者雇用について、法定雇用率を達成していない企業に向けて行政指導も行っています。厚生労働省がサービスを提供しており、全国に500箇所以上の拠点がある支援機関です。国の安定した雇用の維持を目的としており、一般的な雇用だけでなく障がい者雇用にも力を入れています。窓口には、障がいに関する専門知識を持った担当者を配置しているため、採用担当者の考えや職場環境をもとにマッチする職場を紹介してもらえます。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障がい者の職業リハビリテーションや就職支援などを提供している公的な支援機関です。障がい者の就職・定着を支援しており、能力や適性などをカウンセラーが評価・観察しながら向いている仕事を客観的に評価します。就職の際や就職後もジョブコーチを企業に派遣して支援を行っているので、障がい者の離職率を低下できます。障がい者の能力や適性をチェックしながらマッチする人材を雇用したいなら、地域障害者職業センターの利用がおすすめです。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障がい者の就職活動や生活面のサポートを提供している支援機関です。障がい者だけでなく、家族や企業に対しても支援をおこなっている点が特徴です。就職の事前相談から書類作成、面接対策、採用面接への同行などのサポートだけでなく、就職後の定着も支援しています。健康管理についてもサポートしているため、障がい者が安心して働けるようになります。担当者が職場訪問し、人事担当者や上司、同僚に対しての相談・支援も実施している点も特徴です。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障がい者が企業への就職を目指すために訓練や支援を提供している福祉サービス施設です。障がい者が就職するために必要なスキル習得の訓練や職場探し、就職後のサポートなどをおこなっています。企業側が求める人材に合わせて該当する障がい者を紹介してくれるため、即戦力として活躍してもらえる可能性があります。就労移行支援事業所で受講できる訓練にはWordやExcelなどの業務に必要なパソコントレーニングも実施しているので、パソコンを使った業務を割り当てることも可能です。こちらも就労定着支援事業所と同じく利用期間が定められており、期間を過ぎると別の支援機関に引き継がれます。
就労定着支援事業所
就労定着支援事業所は、企業に就職した障がい者が長く働き続けられるようにサポートする福祉サービス施設です。職場だけでなく生活面もサポートしているため、障がい者の定着率を向上できます。障がい者の離職率が高くなると、企業側は新しい人材を採用するためにコストが発生します。就労定着支援事業所は企業と障がい者の調整役であり、就職後のトラブルや不安を解消するために伴走支援をおこなってくれる点が特徴です。ただし、就労定着支援事業所は利用期間が定められているので、期間を過ぎると別の支援機関に引き継がれる点は理解しておきましょう。
特別支援学校
特別支援学校は、障がいのある生徒の教育や生活指導をおこなう学校です。都道府県の教育委員会が管轄しており、小・中・高等学校に相当する教育課程があります。生徒1人ひとりの特性や興味に合わせた就労支援もおこなっており、就職に関するサポートを受けられます。企業側も特別支援学校高等部から在学中に就業体験を受け入れて、卒業時点で採用について検討できるので、特性などを評価しながら紹介してもらうことが可能です。障がい者雇用を進める方法の1つとして、特別支援学校の利用も検討すると良いでしょう。
障がい者雇用支援サービスの選び方
障がい者雇用支援サービスを選ぶ際には、以下のようなポイントを確認することが重要です。
- 実績
- マッチング精度
- 支援内容
それでは詳しく解説します。
実績
障がい者雇用支援サービスを選ぶときは、これまでの支援実績をチェックすることが大切です。障がい者雇用の実績が多ければ、サービスを通じて求める成果が得られます。例えば障がい者雇用数や定着率などの数値が高い場合、企業で長く働ける障がい者を獲得しやすいです。障がい者雇用支援サービスの公式サイトには実績が記載されていることもあるので、利用前に選定基準として一度チェックしてみましょう。
マッチング精度
採用後のミスマッチを防ぐためにも、マッチング精度の高い障がい者雇用支援サービスを選ぶようにしましょう。自社の業界・業種とミスマッチな障がい者を雇用してしまうと、早期離職へとつながってしまう恐れがあります。例えばGreen Link Lab.では、質の高い人材紹介をおこなうために候補者のスキルやコンディション、モチベーション、志向などを細かく分析して紹介しています。入社後の継続的なアセスメントもおこなっているので、採用後のミスマッチを防止可能です。このように障がい者雇用支援サービスによってマッチング精度を高める取り組みがされているため、ミスマッチを防ぐためにもチェックしておきましょう。
支援内容
障がい者雇用支援サービスは、それぞれ提供している支援内容が異なります。障がい者雇用の相談から人材紹介、選考の準備、入社後のアフタフォローなど、利用するサービスによって支援できる範囲は変わります。障がい者雇用支援サービスだけでなく支援機関によっても支援内容は異なるため、どんなサポートを必要とするのかによって利用すべきサービスを選ぶことが大切です。もし求める支援内容がわからないときは、一度障がい者雇用における課題を整理してみると良いでしょう。
障がい者雇用支援サービス・支援機関の対応範囲について
障がい者雇用支援サービスや支援機関では、以下のような対応範囲となっています。
- 人材紹介
- 採用代行
- 定着・活躍支援
- 研修・セミナー
どのようなサポートがあるのかを理解するためにも、ぜひチェックしてください。
人材紹介
障がい者雇用支援サービスや支援機関は、障がい者の特性や希望条件に合わせて求人を紹介しています。企業側の要件と合致する人材紹介をおこなってくれるため、担当者が探す手間をなくせます。
障がい者の種類やスキル、経験、志向などをヒアリングしながら選定してもらえるので、ミスマッチを防ぎながら採用可能です。
利用する障がい者雇用支援サービスや支援機関によっては就職トレーニングが実施されており、即戦力として働ける障がい者の人材を獲得できるでしょう。
採用代行
障がい者雇用支援サービスや支援機関では、企業の代わりに障がい者雇用の採用代行もおこなっています。求人票の作成や採用戦略の策定、面接対策などの採用業務をサポートしてくれるため、企業の採用担当者の負担を軽減できます。また、障がい者雇用に関するノウハウも身につけられるので、社内の担当者が変わったとしても対応することが可能です。企業と障がい者の仲介業者として担当してもらえることから、採用後のミスマッチを防止できます
定着・活躍支援
企業側は障がい者に長く働いてもらうことが重要なので、障がい者雇用支援サービスや支援機関などのサポートを受けることで定着率を向上可能です。
例えば障がい者の特性に合わせた業務マニュアルの整備、健康管理システムの整備、定期的なオンライン面談などのサポートを受けられます。
障がい者が活躍できるような支援をおこなってもらえるため、離職率を低下できます。
企業と障がい者の間から客観的に状況を可視化してもらうこともでき、離職の原因についてアドバイスをもらえる点も特徴です。
研修・セミナー
障がい者雇用支援サービスや支援機関では、企業の従業員に障がい者の理解を深めてもらうために研修やセミナーも実施しています。
障がい者の扱い方について理解してもらうことで、働きやすい環境を整えることができます。差別をなくすことにもつながり、企業は多様性のある働き方を取り入れることができるでしょう。
おすすめの障がい者雇用支援サービス
国内には多くの障がい者雇用支援サービスが展開されているため、企業の担当者は選ぶべきサービスを迷ってしまいがちです。
障がい者雇用は企業と障がい者のニーズを合致させることで、お互いの条件が合った人材を獲得できるようになります。
障がい者雇用と森林保全をテーマとしているGreen Link Lab.では、都市部の企業と地方の障がい者をつなぐ障がい者雇用支援サービスを提供しています。
質の高い人材紹介だけでなく、定着支援や能力開発にも力を入れています。
障がい者雇用を通じて自然災害の抑止や気候変動対策など環境保全活動の活性化にも寄与できることから、企業のSDGs推進活動にもつなげられます。
企業側の障がい者雇用に関する課題解決にもつながるので、ぜひ個別相談もしくは資料請求をお待ちしております。
障がい者雇用支援サービス・支援機関に関するよくある質問
最後に、障がい者雇用支援サービス・支援機関に関するよくある質問について回答します。
- 助成金の申請は可能?
- 支援機関は設定されている?
- 民間企業における障がい者の法定雇用率とは?
疑問を解消するためにも、ぜひ参考にご覧ください。
Q1:助成金の申請は可能?
国や自治体が提供している助成金は、受給要件を満たすことで申請可能です。
障がい者雇用に関する助成金には、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金、キャリアアップ助成金などがあります。
それぞれ助成金の公式サイトに申請方法について記載されているため、障がい者雇用のコストを軽減させたい場合はチェックしておきましょう。
Q.2:支援機関は設定されている?
障がい者雇用支援サービスによってサポートの支援期間は異なりますが、一般的に数週間から数ヶ月程度の期間となることがあります。
詳細については、各サービスの公式サイトから問い合わせてください。
Q.3:民間企業における障がい者の法定雇用率とは?
法定雇用率とは、一定数以上の規模の事業主が雇用すべき障がい者の割合を指します。
現時点で民間企業の法定雇用率は2.5%であり、常時雇用している従業員が40人以上であれば雇用義務があります。
常勤の従業員数によって雇用すべき障がい者数は異なるので、規模に合わせた雇用が必要です。
法定雇用率を達成できなかった場合、ペナルティとしていくつかの罰則規定があります。
法定雇用率は年々引き上げられているため、従業員が一定以上の企業は未達成にならないよう注意しましょう。
まとめ
今回は、障がい者雇用支援サービスや支援機関の選び方について詳しく解説しました。
障がい者雇用支援サービスや支援機関は企業と障がい者を結ぶ役割があり、サポートを受けることで障がい者雇用を促進できます。
とくに障がい者雇用支援サービスを利用すれば、人材紹介や定着支援、研修・セミナーなど幅広いサポートが可能です。
ただし、障がい者雇用支援サービスは豊富にあるため、担当者はどのサービスを選べばいいのか分かりづらい部分もあります。
そんなときは、障がい福祉の専門家であるGreen Link Lab.にぜひ相談をお待ちしております。
監修
鈴木 勇(スズキ イサム)
株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー
1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。
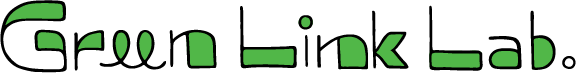
 無料オンライン相談
無料オンライン相談
