【2025年版】発達障がい者の企業向け雇用ガイド|雇用のメリット・注意点・制度・採用定着のポイントを解説
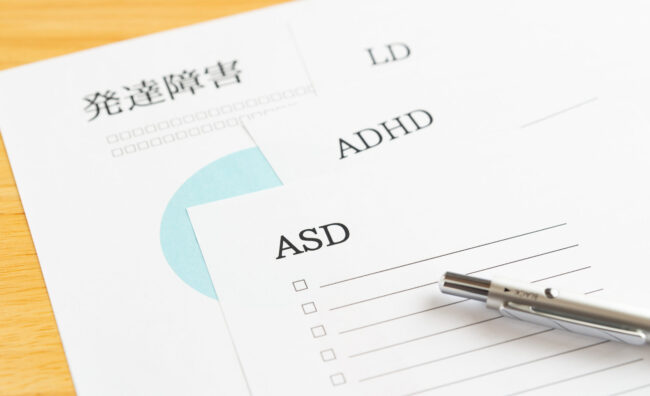
厚生労働省の「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」によると、発達障がいと診断された人は推計で約87万人にのぼり、国内の障がい者約1,160万人のうち1割弱を占めています。
(参考:厚生労働省「意見交換会の基礎資料」)
さらに2025年現在、日本では法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化が進み、障がい者雇用の機会が広がっています。加えて、雇用している人材が新たに発達障がいと診断されるケースも増加しています。
そこでこの記事では、企業が障がい者と向き合うための基礎ガイドとして、発達障がいの主な種類と特性、雇用するメリットや直面しやすい課題を解説します。
目次
発達障がいとは?種類と特性を解説
そもそも発達障がいとは、どのような行動をとる人のことを指すのでしょうか。ここでは、以下に示す3種類の障がい特性について、強みやつまずきのポイントを解説します。
- ASD(自閉スペクトラム症)
- ADHD(注意欠如・多動症)
- LD(学習障がい)
(参考:発達障害情報・支援センター「諸外国の「発達障害」の用語の使用と支援の概要」)
ASD(自閉スペクトラム症)の特性と仕事上の強み・つまずき
ASD(自閉スペクトラム症)は、社会的なコミュニケーションや状況理解に難しさがあり、こだわりや感覚過敏が見られる発達障がいです。
強みとしては、正確さ・規則性を求められる作業や細部への集中力が活かされ、検品やデータ処理などで能力を発揮します。一方で、臨機応変な対応や対人関係を伴う業務ではつまずきやすい傾向があります。
(参考:NCNP病院「自閉スペクトラム症(ASD)」)
ADHD(注意欠如・多動症)の特性と仕事上の強み・つまずき
ADHD(注意欠如・多動症)は、不注意・多動・衝動性が特徴です。
集中力のコントロールに課題があるのに対し、発想力や行動力が豊かで、企画や営業、クリエイティブ業務で強みを発揮します。また、過集中状態では驚異的な集中力を見せることもありますが、スケジュール管理や細かい規則の遵守が求められる業務ではミスや遅れが生じやすい点が課題です。
(参考:NCNP病院「ADHD(注意欠如・多動症)」)
LD(学習障がい)の特性と仕事上の強み・つまずき
LD(学習障がい)は、知的発達に遅れはないものの、読み書き・計算など特定の学習分野に困難を抱える障がいです。LDの人たちは「得意・苦手」がある一方で集中力や創造性、実践力に優れているケースも少なくなりません。
事務作業や文書処理は苦手ですが、空間認識力や創造性を活かせる分野では強みを発揮できます。たとえば体を動かす作業やデザインや模型制作、接客業務などで力を発揮しやすい一方、大量の文字入力や数値処理を伴う業務ではつまずきやすい傾向があります。
(参考:発達障害教育推進センター「学習障害(LD)」)
なお、LDは医学的な診断名ではありません。「特異的な学習の困難さ」という障害の状態です。
特に教育現場で課題が把握されて、学習環境に関する合理的配慮や支援が行われています。発達障害者支援センターでは診断名のあるASDやADHDと比較してLDの相談件数は極端に少ない状態となっています。
| 障がいの種類 | 相談・発達 | 就労 |
|---|---|---|
| 自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障がい | 162件 | 91件 |
| 注意欠陥多動性障がい | 86件 | 47件 |
| 学習障がい | 6件 | 2件 |
出典:発達障がい者支援センター「事業実施状況について(令和6年12月末)」(大阪市)
【グリーンリンクラボ|担当者コメント】
学習障がいを持つ方は、学校での合理的配慮により、不得手なことを補完、代替できた場合には、一定の学力を持ち、自分なりの工夫で社会に出て活躍できる場合があります。この際には、障害者枠でなく、一般就労をしているケースも多くあると思われます。また、発達障がいの特性である「ASD」「ADHD」「LD」は単体ではなく重複してその特性が出てくる場合もあります。
さらに、障がい者雇用の概要や仕組みから詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
発達障がい雇用の現状と企業が直面する課題
近年、発達障がい者の雇用が拡大しており、法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化を背景に企業の採用も増加しています。しかし同時に「人材の強みを活かしにくい配置」「短期間での離職」といった課題も顕在化しています。
以下より、企業が直面する課題や発達障がい者の現状を解説します。
発達障がいの種類と大人・子どもの特徴
発達障がいは前述したASD・ADHD・LDの3種類があり、大人と子どもで次の点が異なります。
| 種類 | 子ども期の特徴 | 大人期の特徴 |
|---|---|---|
| ASD (自閉スペクトラム症) |
・対人関係・コミュニケーション・想像力の困難 ・こだわりの強さや感覚過敏が目立つ |
・冗談や比喩を理解しにくい ・会話が一方的になりやすい ・予定変更への混乱、柔軟性の乏しさ |
| ADHD (注意欠如・多動症) |
・不注意や多動、衝動性による学習のつまずき ・不登校や人間関係のトラブルが起きやすい |
・スケジュール管理や注意の持続が難しい ・整理整頓や期日管理に弱い |
| LD (学習障がい) |
・知的発達に遅れはないが、読み書きや計算の一部に顕著な困難がある | ・文書処理や計算業務で苦手意識が強い |
このように、発達障がいは種類ごとに特徴が異なり、子ども期と大人期で表れ方が変わります。そのため、企業で雇用する際には、診断の有無だけでなく、特性の強さに応じた支援が必要です。
発達障がい者の雇用数・給与・勤続年数の最新データ【2025年】
厚生労働省が公表している「障害者雇用実態調査」によれば、発達障がい者の実雇用数は、平成30年6月時点で推計3万9,000人でしたが、令和5年の調査では推計9万1,000人へと増加していることがわかりました。
(出典:厚生労働省「平成30年度 障がい者雇用実態調査」 / 「令和5年度 障がい者雇用実態調査」)
また、令和5年6月に調査された「障害者雇用実態調査」によると、発達障がい者の平均賃金は13万円です。また月間30時間以上働く通常勤務の障がい者の方は15.5万円が平均となります。
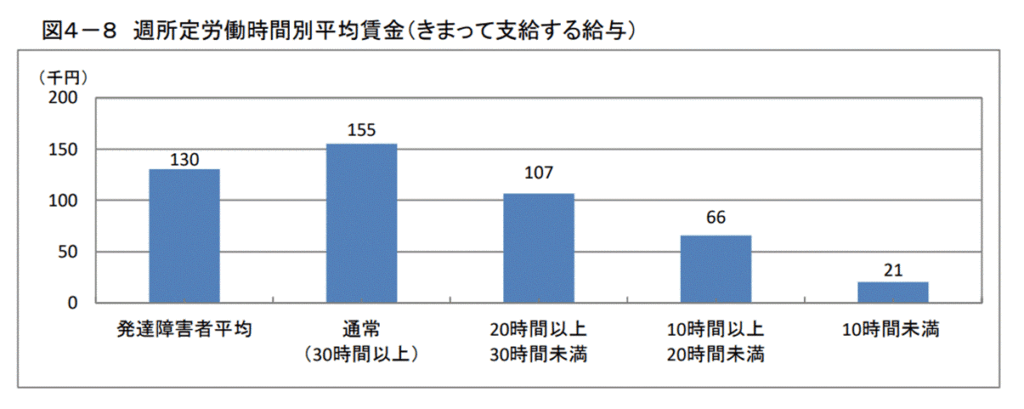
出典:厚生労働省「令和5年 障害者雇用実態調査結果報告書」
加えて同資料の調査において、発達障がい者の平均勤続年数が5年1か月であり、精神障がい者の5年3ヶ月、身体障がい者の12年2か月、知的障がい者の9年1か月と比べると早期離職しやすい傾向にあります。
雇用数は増え続けていますが、給与や勤続年数にはまだ課題が残っています。そのため企業には、「採用」よりも「定着と活躍」へ注力する姿勢が欠かせません。
【グリーンリンクラボ|担当者コメント】
ちなみにハローワークの求職登録では「発達障がい」という区分はなく、療育手帳は知的障がい、精神保健福祉手帳は精神障がいに分類されます。そのため、発達障がい者の雇用数を正確に把握しにくいのが現状です。
一般就労と障がい者枠の実態・違い
発達障がい者が企業で働く際には、大きく分けて「一般就労」「障がい者雇用枠(障がい者枠)」の2つの選択肢があります。
| 項目 | 一般就労 | 障がい者枠 |
|---|---|---|
| 採用のしやすさ | 雇用率制度に依存せず実力評価 | 法定雇用率に基づき採用されやすい |
| 給与水準 | 一般社員と同等水準 | 平均的に低めに設定される傾向 |
| 配慮の有無 | 原則同条件で配慮は限定的 | 業務内容や勤務時間の調整など配慮を受けやすい |
つまり、一般就労は「活躍の幅は広いが配慮は少なめ」、障がい者枠は「配慮は受けやすいが待遇や昇進に制約がある」という違いがあります。
企業側としてはどちらの枠においても、発達障がい者の特性を理解し、適切な合理的配慮を行うことが不可欠です。
また、障がい者雇用には「候補者が集まらない」「定着しない」といった課題がつきものです。グリーンリンクラボでは、独自アセスメントによる質の高い人材紹介と、定着支援・能力開発を通じて、御社の人材課題を解決に導きます。
企業にとって発達障がい者を雇用するメリット
法定雇用率を満たすために障がい者の雇用を検討している企業向けに、発達障がい者を雇用するメリットを3つ紹介します。
【メリット1】強みを活かした専門性・業務貢献
発達障がい者は、障がいの種類に合わせて次のように特性を強みに変えることができます。
- ASD:パターン認識や正確性
- ADHD:発想力や行動力
- LD:他人が気づかない表現・発想力
業務を適切にマッチングすれば、高い集中力や得意分野での専門性を活かし、組織に大きな貢献をもたらします。
【メリット2】ダイバーシティ推進と企業イメージ向上
発達障がいをもつ方に限りませんが、障がい者雇用を進めることで、ダイバーシティ経営の一環として社会的責任を果たすことにつながります。
多様な人材が活躍できる環境を整えるため、社会的評価やブランドイメージが高まり、投資家や消費者からの信頼獲得にもつながるのがメリットです。
【メリット3】法定雇用率の達成
企業にとって法定雇用率を満たすことは義務(2026年は2.7%目標)ですが、発達障がい者の雇用は単なる「数合わせ」以上の意味を持ちます。
特に発達障がい者は、ハローワーク上では精神障がいや知的障がいに区分されるため統計上見えにくい存在ですが、実際には雇用数が増え続けています。
彼らの強みを活かして積極的に受け入れることで、企業は法定雇用率を安定的に達成できるだけでなく、特性を活かした戦力化や多様な人材の活躍の場を広げることにもつながります。
加えて、障がい者全体に対する雇用のメリットを知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
▶ 障がい者雇用のメリット・注意点とは?助成金・課題を企業目線で徹底解説
企業にとって発達障がい者を雇用する課題と解決策
発達障がい者を雇用することには複数のメリットがある一方で、障がいの特性に関する課題もあります。
ここでは、主な課題と解決策を紹介します。
【課題1】ミスマッチによる早期離職リスク
発達障がい者は環境や業務内容との相性が合わない場合、早期離職につながるリスクがあります。実際に身体障がい者の勤続年数が平均12年2か月であることに対し、発達障がい者は5年1か月と短期離職をしやすいのが実情です。
長期に働いてもらうためにも、採用段階での職務適性の丁寧な確認をとり、ジョブカーブ設計、試用期間中のフォローアップを強化することが大切です。
【課題2】職場環境・コミュニケーション対応の負担
発達障がい者は、一般の人よりもコミュニケーションや環境変化に弱さを抱える場合があるため、情報共有や会話における配慮が必要になることがあります。
今後、発達障がい者を雇用する際には、事前に業務マニュアルの明文化やコミュニケーションルールの明確化、ほかにも在宅勤務やフレックスタイム導入など柔軟な対応を行うことが有効です。
発達障がい者の採用面接時に確認すべきこと
発達障がい者を採用する際には、通常の面接での評価項目に加えて「特性の理解度」「仕事内容との適性」「サポート体制」を重視することが重要です。
本項で紹介するチェックポイントを把握しておくことで、採用後のミスマッチや早期離職を防ぎ、安定した雇用につながります。
障がい特性の理解度と自己受容の有無
面接時にまず確認したいのが、応募者本人が自分の発達特性をどの程度理解し、受け入れているかという点です。
特性を正しく認識し、不得意を補う工夫をしている人は、職場に適応しやすい傾向があります。逆に自己理解が浅い場合、ストレス耐性や対人関係で課題が生じやすくなります。
そのため、本人の言葉で「自分はこういう場面が苦手で、こう対処している」と具体的に説明できるかをヒアリングから確認しましょう。
適性のある仕事内容・働き方の確認
次に重要なのが、応募者の特性に合った仕事内容や勤務形態を把握することです。
たとえばASDの方は、ルーチンワークや分析業務に強みを発揮しやすく、ADHDの方は発想力や柔軟な対応が必要な業務で力を発揮することがあります。
事前に「どのような作業が得意か」「どういった職場環境が働きやすいか」を面接で確認することで、配属ミスマッチを防ぎ、長期的な活躍を実現できます。
安定就労につながるサポート体制の必要性
最後に、企業側の支援体制をどう構築できるかも採用可否に直結します。
たとえば、次のような職場は、働きやすい環境を構築できているため、発達障がい者の離職率が下がりやすくなります。
- 定期的な面談
- メンター制度
- 業務マニュアルの整備
- 合理的配慮(環境調整や勤務時間の柔軟化など)
そのため、面接時に「職場からどんな支援があると安心か」を聞き取り、社内で実現可能な体制とすり合わせることが安定雇用につながります。
採用後のミスマッチを防ぐコツ
発達障がい者を採用した際に、後から「思っていた業務と違った」「環境に合わない」などのミスマッチが起こるケースもあります。これを防ぐためには、次のような対策が重要です。
- 採用前に業務内容を具体的に提示する
- ジョブコーチや人事担当者が定期的に確認する
- 合理的配慮を導入する
採用後の定着率を高めたいなら、本人の特性に合わせた環境設計とフォロー体制の整備が欠かせません。企業にとっても人材活用の安定化につながるため、可能であれば採用前に実施しておきましょう。
採用後のミスマッチを減らしたい企業様へ
発達障がい者の採用・定着には、専門的なノウハウと伴走支援が欠かせません。
グリーンリンクラボでは、アセスメントツールを活用した人材紹介から、入社後の定着支援・能力開発までトータルでサポートしています。
発達障がい者の適性の見極めと「おすすめの仕事」
発達障がい者に活躍してもらうためには、特性に合った職務への配置が不可欠です。参考として以下に、ASD・ADHD・LDの特性ごとの強みとおすすめの仕事をまとめました。
| 種類 | 強みを活かせる仕事内容 |
|---|---|
| ASD (自閉スペクトラム症) |
データ入力、検査業務・設計補助、プログラミングなど |
| ADHD (注意欠如・多動症) |
営業、イベント運営、企画職・マーケティング、クリエイティブ職など |
| LD (学習障がい) |
SE、小売店員、製造、清掃、調理補助、介護、軽作業など(いずれも「苦手な部分を補う」こと、「得意な部分を活かす」配置と配慮が必要) |
なお、仕事には合う合わないがあるため、事前に発達障がいの方と面談をし、職場実習制度や試用期間等を活用して、双方で確認できると安心です。
逆におすすめできない仕事
一方で、発達障がいの特性上、不向きな仕事も存在します。無理に従事させると、本人の負担が大きく、企業にとっても早期離職やパフォーマンス低下の原因となります。
- ASD:臨機応変な対応や曖昧な判断が多い接客業、営業職
- ADHD:長時間の単純作業や静かな環境での集中が必須な仕事
- LD:大量の読み書きや計算処理が中心の仕事
ただし、支援ツールや配慮があれば、一部は克服できるケースもあります。重要なのは、「本人の希望」と「職場の配慮可能性」を掛け合わせて判断することです。
発達障がい者に必要な配属・業務設計と職場での合理的配慮
発達障がい者の雇用を安定させるには、採用後の配属や業務設計で「合理的配慮」を取り入れることが欠かせません。
ここでは、企業がすぐに取り組める配慮の例を紹介します。
【配慮1】業務のマニュアル化・明確な指示の準備
発達障がいのある社員は、曖昧な表現や抽象的な指示では混乱しやすい傾向があります。そのため、業務フローをマニュアル化し、作業手順を図や表で示すことが効果的です。
- 指示は短く具体的に伝える
- 作業内容を分解して段階的に提示する
- チェックリストやToDoツールを活用する
こうした取り組みにより、安心して業務に取り組める環境が整います。
【配慮2】感覚過敏や集中力の差に応じた環境調整
ASDやADHDの方は音・光・人の動きに敏感で、集中力を削がれやすい場合があります。職場でできる環境配慮として、次のような対策が挙げられます。
- パーティションやイヤーマフの活用
- 照明の調整や座席配置の工夫
- 在宅勤務や時差出勤の導入
小さな工夫でも生産性の維持につながるため、職場環境の見直しからスタートしましょう。
【配慮3】定期面談とコミュニケーションの工夫
発達障がい者を含む障がい者の多くは「困りごとを自分から伝えにくい」傾向があります。そのため、定期的な1on1面談や相談窓口の設置が重要です。
- 上司・人事担当者が進捗や体調を確認
- 成果だけでなく努力や工夫をフィードバック
- チーム内での役割を明確化し、孤立を防ぐ
こうした仕組みがあることで、本人も安心して働き続けられるようになり、定着率アップを期待できます。
より詳しい配慮の事例をチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです。
▶ 障がいの種類と特性別の特徴・配慮事例|合理的配慮の義務化・職場での具体例・雇用のポイントまで解説
発達障がい者の職場定着を実現する企業マネジメント
発達障がい者を採用したあとに重要なのが、継続的に働いてもらうための「定着」です。
ここでは企業マネジメントの観点から、定着を支える3つの施策を解説します。
評価制度とフィードバックを工夫する
発達障がい者の定着には、評価制度の透明性が大きな影響を与えます。
たとえば、成果だけを重視すると不公平感を抱きやすいため、努力・プロセス・工夫の仕方を評価基準に組み込むことが望ましいです。
また、フィードバックは曖昧な表現を避け、具体的な行動や成果に基づいて行うと理解されやすくなります。チェックリストやフロチャート等の視覚的なツールを用いることも有効です。定期的な面談や1on1を活用することで、モチベーション維持と安心感を提供できます。
グレーゾーン人材への柔軟なアプローチを用意する
発達障がいを抱えている方のなかには、診断を受けていない、いわゆる「グレーゾーン」の人材も多く存在します。
彼らは困りごとを抱えつつも自己申告が難しく、離職リスクが高い層です。メンタルヘルスリスクも高くなります。企業は診断の有無にかかわらず、配慮が必要な人材を包括できる柔軟な仕組みを整える必要があります。
たとえば業務を細分化して誰でも取り組みやすくする仕組みや、相談窓口の開設が効果的です。
外部機関(就労移行支援など)に定着支援を相談する
企業内の工夫だけで限界を感じる場合は、就労移行支援事業所やジョブコーチなど外部機関を活用するのも有効です。
第三者の専門家が介入することで、本人と企業の間に立って調整役を担い、定着率を大きく向上させられます。
また、定着率アップの方法を詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
▶ 障がい者雇用の定着率を高める方法は?離職率の状況や離職理由も解説
発達障がい者の雇用についてよくある質問【FAQ】
発達障がいの人を一般就労(一般枠)で雇うのは難しい?
発達障がいのある人を一般就労で雇うことは、一律に難しいとは言えません。特性に合った業務であれば十分に活躍できる一方、制度的な合理的配慮が明文化されていないため、環境調整が不十分だと離職につながるリスクがあります。企業は事前に業務の適性を確認し、必要に応じた支援体制を整えることが大切です。
発達障がいの人を採用した後に後悔しないためには何をすべき?
採用後に「対応が難しい」と後悔しないためには、採用前後の準備が重要です。面接段階で特性や希望する支援を丁寧にヒアリングし、入社直後はトライアル期間を設けて業務適性を確認します。さらに定期的な面談や社内研修を通じて上司や同僚も理解を深めることで、ミスマッチを防ぎ、定着・活躍につなげることができます。
【よくある誤解】発達障がいは顔つきで判断できるって本当?
発達障がいは脳の情報処理や認知特性に起因するものであり、顔つきや外見から判断できるものではありません。にもかかわらず「顔つきでわかる」といった誤解が広がると偏見や不当な選考につながるので注意してください。
まとめ|「配慮×強み活用」で企業と人材が成長できる職場へ
発達障がい者雇用は、単なる法令遵守ではなく「強みを活かす人材戦略」です。合理的配慮を組み合わせることで、早期離職のリスクを減らし、特性を企業の成長力へとつなげられます。
法定雇用率を満たしつつ、持続可能な経営と人材活躍を両立させるためにも、この機会に「長期的に活躍できる発達障がい者雇用」に取り組んでみてはいかがでしょうか。
障がい者雇用は「コスト」ではなく「未来への投資」です。
監修
鈴木 勇(スズキ イサム)
株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー
1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。
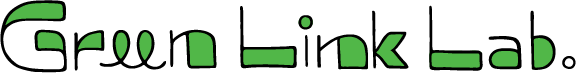
 無料オンライン相談
無料オンライン相談
