【2025年最新】障がい者雇用の定着率を高める方法は?離職率の状況や離職理由も解説
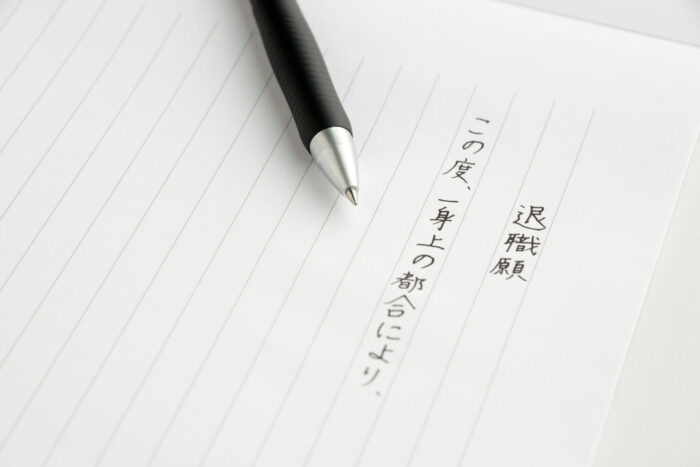
障がい者雇用は年々進展しており、2024年4月からは法定雇用率が2.5%に引き上げられ、さらに2026年7月からは2.7%まで引き上げられる予定です。
しかし、障がいを持つ方を採用したものの「定着しない」「早期離職が多い」と悩む企業は少なくありません。実際、厚生労働省や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の調査でも、一般社員と比べて障がい者の離職率は高い水準にあります。
そこでこの記事では、2025年最新データをもとに、障がい者雇用における定着率・離職率の状況や、一般社員との違い、定着率アップのために企業ができることをわかりやすく解説します。
採用しても定着しない…
そんな課題を抱える企業は少なくありません。
グリーンリンクラボでは、独自アセスメントを活用した人材紹介から、入社後の定着支援・能力開発、さらにはSDGsを意識した企業価値向上のサポートまで、一貫したサービスを提供しています。
目次
企業の定着率を一般社員・障がい者別に紹介【2025年最新】
障がい者雇用の定着率は、一般社員と比べて約3割ほど低い状況です。
| 一般社員の定着率 | 障がい者の定着率 |
| 約88〜89%程度 | 58.4% |
※入社後1年の場合(詳しくは後述)
定着率が低いままでは採用コストが無駄になり、人材不足の解決にもつながりません。一方で、定着率が高い企業は長期的な人材活用に成功し、組織の安定性を確保しています。
そこでまずは、2025年時点で確認できる最新データをもとに、定着率の数値を一般社員・障がい者に分けて整理しました。
障がい者雇用の定着率の計算方法
定着率は、以下の計算式から算出します。
「定着率(%) = (採用後に在籍している人数 ÷ 採用人数) × 100」
たとえば、2024年度に障がい者を10人採用し、そのうち1年後に7人が在籍していれば、定着率は70%です。
一般社員の企業定着率(厚生労働省)
厚生労働省が公開している資料によると、2024年の一般労働者の入職率は11.8%、離職率は11.5%でした。
前年(2023年)はともに12.1%であったため、定着率はわずかに改善したことがわかります。また性別で見ると、男性(入職率12.9%、離職率12.6%)よりも女性(入職率16.8%、離職率16.0%)の方が活発に出入りしています。
これらのデータを踏まえると、一般労働者の定着率はおおむね88〜89%程度と推測されます。(離職率 11.5% → 残存率(定着率) ≒ 100 − 11.5 = 88.5%)
(出典:厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」)
障がい者の企業定着率(NIVR)
独立行政法人・職業リハビリテーション研究・研修センター(NIVR)が実施した調査によると、障がい者の定着率は一般社員に比べて、低い水準にあることが明らかになっています。
以下に、障がい者雇用後の離職率の傾向を整理しました。
- 就職後3か月時点:76.5%(A型含むと80.5%)
- 就職後1年時点:58.4%(A型含むと61.5%)
つまり、就職から1年以内に約4割が離職してしまう現状です。法定雇用率を満たすためにも、企業は継続的に定着率の維持・向上に努めなければなりません。
(出典:NIVR「調査研究報告書 No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究」)
【グリーンリンクラボ担当者コメント】
同調査によると、1年以内の離職者の69.3%が“自己都合”でした。特に就職から3か月未満で離職するケースでは、労働条件が合わない(19.1%)、業務遂行上の課題(18.1%)が多く見られます。つまり、採用直後は「マッチング不足」が原因となりやすく、定着までの中期では「健康・体調の維持」が課題になるケースが多いようです。
企業の離職率を一般社員・障がい者別に紹介【2025年最新】
前述した定着率とは別の視点として「一般社員と障がい者の離職率」の傾向を、国の情報ベースで整理しました。
企業にとって、離職率の把握は即時の人材リスクを評価するうえで不可欠な要素です。特に障がい者雇用では、一般社員との比較だけでなく、障がい別や雇用形態別の違いも含めて定着の施策を考えることが欠かせません。
一般社員の離職率(統計局)
厚生労働省が公開している資料では、2024年の一般労働者の離職率は11.5%でした。(前述でも解説)
(出典:厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」)
また補足として、総務省統計局「労働力調査」では、完全失業率(やめた後に無職になっている割合)が2.3~2.5%と安定水準にあり、就業者数は前年同月比で51万人増加しています。
| 区分 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||
| 完全失業率 | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.3% |
出典:総務省統計局「労働力調査(2025年8月公表)」
つまり、離職自体は一定数あるものの、景気や雇用環境が堅調なため、失業率は低位で推移している(多くの人たちが再就職を果たしている)のが2025年の状況です。
障がい者の離職率(厚生労働省)
障害者職業総合センター(NIVR)の調査によると、障がい者の離職率は一般労働者と比べ、依然として高い水準にあります。
以下に前述した定着率から計算できる離職率を整理しました。
- 就職後3か月定着率:76.5% → 離職率23.5%
- 就職後1年定着率:58.4% → 離職率41.6%
(出典:NIVR「調査研究報告書 No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究」)
つまり、一般社員の離職率11.5%と比較すると、2〜4倍程度の差が生まれます。特に就職後1年以内の定着が課題です。
障がいの種類別にみる定着率・離職率の違い
障がい者の定着率や離職率は、障がいの種類によって大きな差がみられます。
障害者職業総合センターの調査資料をもとに、障がいの種類ごとに定着率と離職率の違いを整理しました。
(出典:NIVR「調査研究報告書 No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究」)
身体障がい者の定着率・離職率
身体的な障がいを抱える方の場合、定着率は以下の通りです。
- 3か月定着率:77.8%(離職率22.2%)
- 1年定着率:60.8%(離職率39.2%)
身体障がい者は、比較的安定して就業を継続する傾向があります。
ただし、健常者(一般社員)の1年定着率と比べると依然として低く、職場環境や合理的配慮の不足が離職要因となるケースも見られます。
精神障がい者の定着率・離職率
統合失調症や依存症など、精神的な障がいを抱える方の場合、定着率は以下の通りです。
- 3か月定着率:69.9%(離職率30.1%)
- 1年定着率:49.3%(離職率50.7%)
精神障がい者は、1年経過時点で定着率が50%を下回り、もっとも離職率が高い傾向にあります。
また、短期では「労働条件が合わない」「業務遂行が困難」、1年以内では「障がいや病気のため」といった理由が目立ち、職場での支援や配慮の有無が定着の分かれ目となります。
知的障がい者の定着率・離職率
知能の遅れといった知的な障がいを抱える方の場合、定着率は以下の通りです。
- 3か月定着率:85.3%(離職率14.7%)
- 1年定着率:68.0%(離職率32.0%)
知的障がい者は、初期3か月の定着率がもっとも高く、早期離職の割合は少ない傾向にあります。
しかし、1年後には約3割が離職していることから、業務内容やサポート体制との適切なマッチングが長期定着に欠かせません。
障がい者雇用における定着率と法定雇用率との関係
ここまで「定着率」「離職率」の実態を見てきましたが、企業にとって特に重要なのが、定着率・離職率が法定雇用率の維持に直結するという点です。
たとえば、従業員100名の会社で法定雇用率(2025年時点で2.5%必要)を満たすために、3名の障がい者を採用したとします。この時点では雇用率3.0%で基準をクリアしています。
しかし、1年以内に1名が離職した場合、障がい者雇用数は2名となり、雇用率は2.0%に低下します。すると、法定雇用率を下回る状態となり、新たな採用を急ぐ必要が生じるだけでなく、場合によっては納付金や指導の対象となる可能性もあります。
【グリーンリンクラボ担当者コメント】
法定雇用率を満たせなかった企業は、納付金(いわゆる罰金)を支払わなければなりません。(不足する人数×5万円/月)
(参考:高齢・障がい・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」)
このように、企業は「雇用率を満たすための採用」だけでは十分ではありません。
雇用した障がい者が職場に定着し、安定して働き続けられる環境を整えることこそが、持続的な雇用率維持と企業経営の安定につながります。
障がい者を雇用しても定着率が上がらない(定着しない)理由とは?
障がい者雇用を進めても、実際には定着率が思うように上がらないケースが多く見られます。
その背景には、本項で紹介する4つの理由が関係しているかもしれません。
【理由1】職場の雰囲気や人間関係の問題
もっとも大きな要因のひとつが、職場での人間関係の摩擦や孤立感です。
障がいに対する社員の理解不足により、同僚や上司とのコミュニケーションが円滑にいかず、早期離職につながるケースもあります。
特に、配慮が形だけにとどまってしまうと「居場所がない」と障がい者に思われやすくなります。
【理由2】賃金・労働条件に関する不満
次のように、労働条件が本人の希望と合わない場合も、定着を妨げる大きな要因となり得ます。
- 給与水準の低さ
- 勤務時間の長さ
- 休暇の取りにくさ など
障がい特性に応じた柔軟な勤務形態(時短勤務や在宅勤務など)が整っていないと、離職率が上がりやすくなります。
早期離職の原因となるため、雇用前に障がい者と意見調整を行うことが大切です。
【理由3】業務内容と適性の不一致
障がい者は、障がい特性やスキルに合わない業務に従事すると、業務遂行が困難となり、強いストレスや不安を感じやすくなります。
その結果、短期間での離職に至るケースがあり、障害者職業総合センターの調査資料でも「業務遂行上の課題」が、3か月未満で離職する障がい者の18.1%が離職理由として挙がっています。
(出典:NIVR「調査研究報告書 No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究」)
【グリーンリンクラボ担当者コメント】
働きたい仕事との不一致を避けるためにも、企業や担当者は、業務の定期的な見直し・追加による「成長できる仕組みづくり」に取り組むことが大切です。より詳しい動き方は、以下の記事で解説しています。
▶ 障がい者雇用の業務切り出し完全ガイド|6ステップ・事例・助成金・注意点を徹底解説
【理由4】健康面・精神的ストレスの影響
障がいの状態や持病の悪化、通勤負担、過度なストレスは、就労継続を困難にする原因となり得ます。
特に精神障がいの場合、体調の波やストレス耐性の低下が離職の直接要因になりやすく、定期的なフォローや医療機関との連携が欠かせません。
このように、定着しない理由は「本人の問題」ではなく、職場環境や制度設計の不足に起因することが多い点を押さえることが重要です。
【失敗から学ぶ】企業が離職率を下げるよくある失敗例
障がい者雇用を進める企業のなかには、善意で取り組んでいるにもかかわらず、離職率が高止まりしてしまうケースがあります。
その多くは「ちょっとした配慮不足」や「採用段階でのミスマッチ」が原因です。ここでは代表的な失敗例を紹介します。
【失敗例1】形だけの配慮で職場環境改善が不十分
障がい者雇用を推進するために、机の配置や勤務時間を一部調整するなど「表面的な配慮」にとどまってしまう企業は少なくありません。
しかし、実際には次のようなギャップが起こり、働きやすさに直結せず、むしろ障がい者に疎外感や不安を抱かせる要因となっています。
| 形だけの配慮例 | 影響 |
| 配慮はしたけど職場全体の理解が足りなかった | 通路を広げて車いすが通れるようにしたものの、「仕事のフォローは誰がするのか」「一緒に働く負担が増えるのでは」といった周囲の不満が残り、職場全体の雰囲気が悪化してしまう |
| 制度はあるが現場で活用されなかった | 会社として時短勤務制度を整備しても、現場の上司が「人手が足りないから通常勤務で頼む」と実質的に利用を妨げてしまい、結果的に体調を崩して離職につながる |
| 配置転換だけで終わってしまった | 「負担を軽減するために軽作業へ異動」としたが、実際には単調すぎる作業でやりがいを失い、モチベーションが下がって短期離職につながる |
このように、制度設計と職場運用の間にズレがあると、せっかくの配慮が逆効果となり、定着率を下げる原因になります。企業は「形だけ」ではなく、現場で実効性のある仕組みづくりを徹底しなければなりません。
【失敗例2】採用時にミスマッチが起きやすい
障がい者雇用の枠を埋めることを優先し、業務内容や本人の適性を十分に確認せず採用した結果、障がい者の定着率を下げてしまうケースもあります。
特に、雇用を希望する障がい者とのミスマッチで、次のようなトラブルへと発展します。
- 事務作業を任せたが、パソコン操作が苦手で業務に負担がかかった
- 接客業務に配置したが、対人ストレスが強く、数か月で離職してしまった
- 体力を要する現場作業に配属したが、健康面の配慮不足で長期勤務できなかった
こうした「仕事と人のミスマッチ」は、障がい者本人にとっても企業にとっても不幸な結果を招きます。採用段階で適性評価や実習を行い、業務内容との整合性を確認することが欠かせません。
【失敗例3】職務設計・キャリアパスを調整しない
障がい者雇用を進めても、「毎日同じ単純作業だけ」「将来の役割が見えない」といった状態を続けてしまうと、働く本人の意欲が下がってしまいます。
なかには「ここで成長できない」と感じ、離職につながるケースも少なくありません。企業としては「負担を減らすために簡単な作業を任せたつもり」が、逆に本人のやりがいを奪ってしまう落とし穴になることもあります。
障がい者を雇用する際には、その人の得意不得意を可視化したうえで適切に職務を設計することが大切です。さらに将来のキャリアパスを意識し、定期的に業務を見直すことで、本人が「ここで成長できる」と感じ、離職防止につながります。
障がい者雇用の定着率を高めるために企業ができること
障がい者雇用後の定着率を高めるためには、「採用」「職場環境」「人間関係」「外部連携」の4つの視点で取り組むことが重要です。
単なる制度導入にとどまらず、以下で紹介するような「現場で実際に活用される仕組み」にすることで、離職率を下げ安定した雇用につながります。
【アイデア1】採用時のマッチング精度を高めて離職率を下げる
障がい者雇用後の離職率を下げたい場合には、採用段階から適性や希望を丁寧に把握し、業務との相性を確認することが大切です。
たとえば、短期実習やトライアル雇用を通じて実際に働いてもらうことにより、本人・企業双方が「無理なく続けられるか」を見極められます。
また、実際に業務を体験したうえで継続か否かを判断してもらえるため、早期離職のリスク回避はもちろん、障がい者雇用に欠けるコストを必要最小限に抑えられるのが魅力です。
【アイデア2】ICT活用やバリアフリーで働きやすい職場環境を整える
障がい者の物理的・心理的な障壁を取り除くためには、社内の設備・制度の整備が欠かせません。
たとえば、車いすでも移動しやすい通路やトイレの設置、音声認識ソフトや在宅勤務制度の導入など、個々のニーズに合わせた環境づくりが必要です。
現場で実際に使いやすいかどうか、定期的に見直すことも重要です。
【アイデア3】管理職や同僚への研修で社内理解を深める
職場における人間関係の理解不足は離職の大きな原因となるため、次の方法で障がい者雇用の理解を促すことも大切です。
- 障がい特性理解研修
身体・知的・精神・発達障がいそれぞれの特性と職場で起こりやすい課題を学ぶ - 合理的配慮の実践方法
勤務時間の柔軟化、業務分担、声かけの工夫など実際の事例を学ぶ - ハラスメント防止研修
障がいを理由にした不適切な言動や対応の具体例とNG行動を学ぶ - 管理職向けリーダーシップ研修
配置・評価・キャリア形成の視点から障がい者を戦力化する方法を学ぶ
事前に情報共有ができていれば、配慮の仕方や声掛けの工夫が広がり、障がい者の孤立感の解消につながります。単なる「制度の周知」ではなく、日常業務の中でどうサポートするかを学ぶことが肝心です。
【アイデア4】支援機関と連携して障がい者が相談しやすい体制をつくる
障がい者雇用や定着率の課題は、職場だけで問題を抱え込むのではなく、外部支援機関と連携して支援体制を整えることも有効です。
たとえば、地域障害者職業センターや就労移行支援事業所などとつながることで、本人が安心して相談でき、困りごとが大きくなる前に解決できます。企業にとっても、専門的な助言を受けながら長期雇用を実現するサポートを得られます。
また社内だけでの対応が難しい場合には、厚生労働省が提供している「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業」を利用できます。職場にジョブコーチが出向いて、障がい特性を踏まえた専門的な支援を行い、障がい者の職場適応を図れます。
(参考:厚生労働省「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について」)
【アイデア5】モチベーション維持のために業務を工夫する
障がい者が安心して長く働き続けるには、「成長できる」「やりがいがある」と実感できる仕組みが欠かせません。
たとえば次のように、単純作業だけを任せ続けるのではなく、本人が成長を感じられる工夫を取り入れることが、モチベーション維持につながります。
- 段階的に業務をステップアップする
補助作業から始めても、習熟に応じて責任のある業務へと広げる - キャリアの見通しを示す
「数年後にはリーダー補佐」「専門担当」など将来像を伝える - 成果をこまめに評価・フィードバックする
小さな達成も見逃さずに言葉や制度で認める - スキルアップの機会を提供する
研修や資格取得支援などで「できることが増える」実感をもたせる
上記のような取り組みを積み重ねることで、本人が「ここで成長できる」と感じられるようになり、結果的に定着率の向上に直結します。これは離職リスクを減らすだけでなく、企業にとっても長期的な人材活用につながります。
離職率の高さに悩んでいませんか?
グリーンリンクラボでは、独自アセスメントを活用した人材紹介や、入社後の定着支援・能力開発の仕組みづくりなど、実際に効果があった改善策をもとに御社に合わせた具体的なアドバイスをご提案します。
障がい者の定着率向上に成功した企業事例一覧
障がい者雇用は「採用すること」以上に「定着させること」が難しいと言われています。
しかし、実際に定着率向上に成果をあげている企業も数多く存在します。ここでは、高齢・障がい・求職者雇用支援機構(JEED)のケースブックをもとに、事例を整理しました。
| 企業名 | 障害種別 | 主な取組 | 成果・定着率への効果 |
| 株式会社ダイキンサンライズ摂津 | すべての障がい | ・サブリーダー制導入 ・相談窓口「みどりの時間」を設置し、複数の相談経路を確保 |
障がいの種類に関わらず職場定着率が大幅に改善。社員が体調変化を共有しやすくなり、安定した業務運営を実現。 |
| 株式会社ダイキンサンライズ摂津 | 精神障がい中心 | ・業務日誌+Web日報システム「SPIS」により体調変化を可視化 | 精神障がい者の定着率改善に効果。体調変化を早期に発見・共有でき、労働意欲向上と長期就業に寄与。 |
| 太洋リネンサプライ株式会社 | すべての障がい | ・障がい者職業生活相談員を複数配置し、LINE WORKSで支援体制を構築 | 平均勤続年数:障がい者24年8か月。定着率が2倍近くに向上。 |
| 王将ハートフル株式会社 | 知的障がい | ・リーダー・サブリーダーの資格取得支援、勉強会・ジョブコーチ養成研修 | 障がいのある社員のスキルが向上し、支援が減少=自立度上昇=長期定着化。 |
| AIGハーモニー株式会社 | すべての障がい | ・単純作業中心からの脱却を目指し、工程を分解して幅広い業務に挑戦できる仕組みを整備 ・進捗を可視化し、勉強会で障がい理解を促進 |
同じ作業ばかりで意欲を失っていた社員が、多様な工程に対応できるようになり、モチベーション向上と定着率改善につながった。 |
出典:高齢・障がい・求職者雇用支援機構「中小企業における障害者の職場定着推進のための職場改善ケースブック(令和5年度)」
各事例からわかるように、定着率向上を実現している企業は、単なる制度導入ではなく「現場で使える仕組み」や「人を介したサポート体制」に力を入れています。
「採用後のサポート設計」と「現場での理解・協力」を両輪で進めることが、結果として定着率の改善=法定雇用率の安定につながるのが特徴です。
障がい者雇用の定着率についてよくある質問【FAQ】
障がい者雇用の定着率はどのくらいですか?
独立行政法人・職業リハビリテーション研究・研修センターの調査によると、就職後3か月時点では76.5%ですが、就職後1年になると58.4%まで低下します。一般社員よりも定着率が下がることから、離職率を下げる対策が欠かせません。
精神障がい者の定着率が低いのはなぜですか?
体調の変動や職場での理解不足、コミュニケーションの難しさが要因とされます。一例として、相談窓口や支援員の配置で改善する企業事例もあります。
障がい者雇用の定着率はどうやって計算するのですか?
「採用から一定期間(1年など)勤務を継続した人数 ÷ 採用者数」で算出します。勤続年数別に追跡し、安定性を測ることもあります。
障がい者の雇用が進まない理由は何ですか?
仕事内容の切り出し不足や職場環境の未整備、人材育成の仕組みが不十分であることが大きな理由です。誤解や偏見が残るケースもあります。
企業が障がい者雇用で定着しない原因を防ぐには?
相談しやすい窓口の設置、支援員の育成、体調把握の仕組みづくりが効果的です。加えて、スキル向上の機会を提供し、やりがいを感じられる職場づくりが重要です。
まとめ|障がい者への配慮が定着率・法定雇用率の向上につながる
障がい者を雇用し、国が定める法定雇用率を満たし続けるためには、採用以上に「定着させる仕組みづくり」が重要です。
本記事で紹介した情報や事例からもわかるように、相談窓口や支援体制の整備、ジョブサポーター制度、リーダー層の育成、ITツールを活用した体調管理などが定着率アップに直結しています。
多くの企業が定着率改善に成功しているのは、専門家と一緒に課題を見える化し、具体的な改善策を実行したからです。
グリーンリンクラボの無料相談では、独自アセスメントを活用した人材紹介や入社後の定着支援・能力開発など、貴社の状況に合わせた実践的な施策をご提案します。
監修
鈴木 勇(スズキ イサム)
株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー
1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。
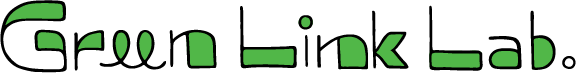
 無料オンライン相談
無料オンライン相談
