【2025年最新版】障がい者雇用×SDGs|関係する6つの目標と課題・企業が取るべき具体策・事例を徹底解説

「障がい者雇用」は、SDGs(持続可能な開発目標)が掲げる「誰一人取り残さない社会」を実現するための大切な取り組みです。
そして2025年現在、日本では法定雇用率の引き上げや合理的配慮の義務化が進んだことにより、世界的にも雇用の質と多様性が企業価値を左右する時代に入りました。しかし、実際には企業で「雇用機会の不足」「職場のバリアフリー対応の遅れ」などの課題が残っています。
そこでこの記事では、障がい者雇用とSDGsがどのように結びついているのかをわかりやすく解説します。
目次
障がい者雇用と「誰一人取り残さない」SDGsの基本
障がい者雇用は、SDGsの理念を具体的に体現する取り組みです。
たとえば、日本の人口の約10%を占める障がい者は、教育や就労機会の制約を受けやすく、社会的排除のリスクが高い層でもあります。
(出典:厚生労働省「意見交換会の基礎資料」)
日本では「障害者雇用促進法」によって、大きな会社には一定の割合で障がい者を雇う義務があります。なお現在の法定雇用率は2.5%ですが、2026年からは2.7%に上がる予定です。
(参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)
ちなみに企業が実施する障がい者雇用は、SDGsの目標である教育(目標4)・働きがい(目標8)・不平等是正(目標10)などに関わります。
単なる義務ではなく企業価値向上や国際的評価にも影響するため、法定雇用率を下回っている企業は、将来のためにも法定雇用率を満たすことが重要です。
採用はできる。 でも“定着”に困っていませんか?
グリーンリンクラボでは、採用後の定着支援と能力開発を重視。 「雇う」だけでなく「活躍し続ける」仕組みづくりをサポートしています。
日本と世界におけるSDGsの進捗状況【2025年】
2025年現在、SDGs(持続可能な開発目標)は「進展しているが未だ十分ではない」という状況です。
まず、日本の内閣官房・外務省で公開されている「自発的国家レビュー(VNR)」によると、健康(目標3)、雇用と経済成長(目標8)、産業・イノベーション(目標9)、気候変動対策(目標13)で進展が見られる一方、次の課題がいまだに残っている状況です。
- ジェンダー平等(目標5)
- 不平等の是正(目標10)
雇用と経済成長(目標8)は改善していますが、不平等の是正(目標10)はまだ課題が残っています。
(参考:内閣官房・外務省「SDGs に関する自発的国家レビュー(VNR)報告書」)
また世界的な進捗状況として、国連は「SDGs報告2025」を発表しました。この10年間で教育・保健・エネルギー、デジタル分野における成果は評価されていますが、全ターゲットのうち順調に進んでいるのは35%です。半数近くが遅延、18%が後退しているなど、まだまだSDGsの目標達成には時間がかかると予想されます。
(参考:国際連合広報センター「SDGsは過去10年間で何百万もの人々の生活を向上させたが、前進は依然として不十分―国連報告書が指摘」)
SDGsで障がい者雇用に関わる6つの目標とは?
SDGsには合計17種類の目標・ゴールが設定されていますが、障がい者雇用に関わるポイントは以下の6種類です。
| SDGs目標 | 障がい者雇用との関係 | 社会・企業への効果 |
|---|---|---|
| 目標1 貧困をなくそう | 安定した収入の確保により、貧困の連鎖を断ち切る | 生活基盤の安定、福祉依存の軽減 |
| 目標3 すべての人に健康と福祉を | 医療・福祉と連携して雇用を継続 | 雇用定着率向上、生活の質向上 |
| 目標4 質の高い教育をみんなに | 学習機会や職業訓練を確保 | スキル習得・就労選択肢の拡大 |
| 目標8 働きがいも経済成長も | 障がい者雇用の中心的な目標 | 働きがいの実感、企業の成長に貢献 |
| 目標10 人や国の不平等をなくそう | 差別や偏見の解消、平等な機会保障 | 多様性経営の推進、ブランド価値向上 |
| 目標17 パートナーシップで目標を達成しよう | 官民・教育機関・NPOの連携による雇用拡大 | 持続可能な雇用モデルの構築 |
このように、障がい者雇用は、SDGsのなかでも「働きがい」「不平等の是正」「教育」「健康」といった目標と密接に関係しています。
また、単に雇用の数を増やすだけでなく、教育や福祉との連携、バリアフリー環境の整備、官民連携による支援が不可欠です。これらを実践することで、障がい者本人の生活基盤が安定し、企業のブランド価値や競争力の向上にもつながります。
(参考:日本ユニセフ協会「SDGs17の目標|SDGsクラブ」)
企業が把握すべき障がい者が抱える課題
企業が障がい者雇用を進める際には、事前に障がい者が抱える次の課題を理解しておくことが重要です。
- 雇用機会の不足と職種の偏り
- 職場のバリアフリー・ICT対応の遅れ
- 障がい者差別と偏見
- 発達障がいへの理解不足と就労支援不足
ここでは、企業が把握しておくべき課題をひとつずつ解説します。
「採用したのに定着しない」
「どう育成したら良いかわからない」
そんな課題には、専門家の伴走が必要です。 グリーンリンクラボは独自アセスメントと継続支援で、安心して働き続けられる環境を構築します
【課題1】雇用機会の不足と職種の偏り
障がい者が直面する課題のひとつが「雇用機会の不足」と「職種の偏り」です。
厚生労働省が公開している「障害者雇用状況の集計結果」によると、業界別の雇用率は2〜3%程度と安定しています。
| 業種 | 障がい者雇用者数(人) | 実雇用率(%) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 約163,000人 | 2.32% | 全産業で最多。大規模工場やライン作業などで雇用しやすい。 |
| 卸売業・小売業 | 約96,000人 | 2.21% | 「品出し」「清掃」「接客補助」等の補助業務を中心に職域を形成。 |
| 医療・福祉 | 約98,000人 | 3.09% | 実雇用率が高く、介助・補助業務などで活躍の場が多い。(障害福祉サービスの就労継続支援A型も含む) |
出典:厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」
しかし実際には、事務補助や清掃など限られた補助的な仕事に集中してしまう傾向があります。
望まない仕事への雇用は定着率の低下を招くため、障がい特性に応じた適性把握と配置の工夫に取り組むのはもちろん、多様な職種におけるチャレンジの機会を提供しましょう。
なお障がい者ごとの特性を詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
▶ 【2025年版】障がいの種類と特性別の特徴・配慮事例|合理的配慮の義務化・職場での具体例・雇用のポイントまで解説
【課題2】職場のバリアフリー・ICT対応の遅れ
障がい者に長く働き続けてもらうためには、次のような物理的・デジタルの両面でバリアを取り除くことが不可欠です。
- 身体障がい者が利用しにくい階段の改善(スロープ・手すりなど)
- 複雑で理解しづらい作業のマニュアル化・スケジュール化
しかし、日本の現場では上記の物理的バリアフリー化が不十分であるだけでなく、ICT(情報通信技術)の対応も遅れています。
こうした環境整備が遅れると、障がい者は本来のスキルを発揮できず、職場への定着率も下がります。人材の流出や雇用率未達という問題を抱えることになるため、事前に対策を取るなど、リスクヘッジに取り組むことが大切です。
なお、定着率を高める方法については以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 障がい者雇用の定着率を高める方法は?離職率の状況や離職理由も解説
【課題3】障がい者差別と偏見
障がい者雇用の現場では、採用時だけでなく就職後のキャリア形成においても差別や偏見が残っています。表面的には平等に扱われているように見えても、実際には「昇進の機会が少ない」「責任ある仕事を任せてもらえない」といった見えない壁が存在します。
そのため、社内研修や外部セミナーの参加を制限されたり、ジョブローテーションから外されたりするなど、就職後に必要なステップアップやスキル習得の機会を得にくくなる点に注意しなければなりません。
障がい者が採用から昇進・管理職登用まで一貫して活躍できる環境を整備するためにも、障がい者を含む公平な人事評価制度の導入や、学習機会・研修プログラムの平等な提供に力を入れることが大切です。
【課題4】発達障がいへの理解不足と就労支援不足
複数ある障がいのなかでも「発達障がい」は、大学や専門学校を卒業して社会人になってから気づくケースが増えています。
そのため、雇用後に「職場でのコミュニケーションについていけない」「業務の優先順位づけが苦手で注意を受けることが多く評価が下がる」といった困難を経験する人も少なくありません。
発達障がいは「本人の努力不足」ではなく、ひとつの障がいの形です。環境次第で強みを発揮できる特性があるため、職場での合理的配慮や管理職や同僚への発達障がいに関する研修の実施など職場での啓発活動も合わせて行うと良いでしょう。
SDGsを考慮した障がい者雇用対策一覧
障がい者雇用を進める際には、単に「法定雇用率を満たす」だけでは不十分です。次のようにSDGsの視点を取り入れることで、企業の社会的責任を果たしつつ、多様な人材が活躍できる職場づくりが可能になります。
| 対策内容 | SDGsとの関連 | 具体的な取り組み例 |
|---|---|---|
| 雇用機会の創出 | 目標8「働きがいも経済成長も」 | 障がい者専用の採用枠設置、インターン制度の導入 |
| 職場環境の改善(バリアフリー化・ICT活用) | 目標10「人や国の不平等をなくそう」 | 段差解消、音声読み上げ・入力支援ソフトの導入 |
| 研修・教育プログラムの整備 | 目標4「質の高い教育をみんなに」 | 社員向け障がい理解研修、スキルアップ研修 |
| 公正な評価とキャリア支援 | 目標5「ジェンダー平等」+目標10「人や国の不平等をなくそう」 | 昇進の機会を均等に提供、ジョブコーチ活用 |
| 社外との連携 | 目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」 | 行政・就労支援機関・NPOとの連携 |
| 健康と福祉のサポート | 目標3「すべての人に健康と福祉を」 | 産業医・カウンセラー配置、メンタルヘルス支援 |
このようにSDGsを意識した施策を進めることで、障がい者の就労定着率向上・企業のブランド強化・人材不足解消といった効果が期待できます。
SDGsを考慮して障がい者雇用を進めるメリット
ただ障がい者の雇用率を増やすのではなく、そこにSDGsの目標や考えを取り入れるメリットを紹介します。
【メリット1】企業ブランド・評価の向上
障がい者雇用に取り組めば、採用力や従業員のエンゲージメント向上につながるのがメリットです。
まず、企業が障がい者雇用に積極的に取り組めば、社会的責任を果たすことになり、投資家や顧客、取引先企業などからの評価を得やすくなります。
「誰もが安心して働ける会社」というイメージが生まれ、求職者からも魅力的に見えます。
【メリット2】人材不足解消と多様性によるイノベーション
障がい者雇用は、深刻化する人材不足の解消に直結します。特に日本では少子高齢化の影響で労働力人口が減少しており、多様な人材の活用が不可欠です。
また、障がい者が持つ多様な視点や経験は、新しいアイデアや製品開発の源泉になります。日本財団の調査でも、障がい者を積極的に雇用する企業ほど、顧客満足度や従業員満足度が高い傾向が確認されています。
「誰もが安心して働ける職場づくり」を進めることは、採用力の強化だけでなく、イノベーションを生み出す組織風土の醸成にもつながります。
【メリット3】コンプライアンス遵守と法令違反リスク回避
障がい者雇用に取り組めば、単に社会的責任を果たすだけでなく、法令遵守とリスク回避という観点で大きなメリットがあります。
日本では、障害者雇用促進法にもとづき、一定規模以上の企業に法定雇用率の達成が義務付けられています。まず未達成の場合、不足する人数×5万円/月の納付金を支払わなければなりません。
(出典:厚生労働省「障害者雇用納付金制度の概要」)
また、障がい者雇用の改善が見られない企業に対しては、企業名の公表といったペナルティもあります。
(出典:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」)
対して、法定雇用率を満たすように障がい者雇用に取り組めば、上記のペナルティをまるごと回避できます。逆に、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合には、超過している人数×2万3,000円/月の調整金を受け取ることが可能です。
また障害者雇用促進法以外にも、障がい者雇用をする際にはさまざまな法律の理解が必要です。人事担当者として把握しておきたい法律を、以下の記事で紹介しています。
▶ 人事担当者が知っておきたい障がい者雇用に関する法律について
また、障がい者雇用の詳しいメリットは以下の記事でより詳しく説明しています。
▶ 障がい者雇用のメリット・注意点とは?助成金・課題を企業目線で徹底解説
SDGsを考慮して障がい者雇用を進める際の注意点
障がい者雇用をSDGsの観点から推進する際には、単に「数を満たす」だけでは不十分です。形だけの雇用では長続きせず、会社のイメージ低下や社内の不信感を招くこともあります。
ここでは、特に注意すべき4つのポイントを整理します。
- 形式的な雇用にしないこと
実際に働きがいを感じられる職務内容や環境を整備する - 短期的な数字合わせを避けること
一時的な雇用率達成ではなく、継続的なキャリア形成支援を意識する - 社内理解を浸透させること
管理職や同僚の無理解が、職場での摩擦や孤立を生みだすため、研修や情報共有が欠かせない - SDGs目標との関連性を共有すること
「自分の仕事がSDGsにどう役立っているのか」を理解してもらう
「雇用率を満たすだけでなく、本当に持続可能な仕組みをつくりたい」とお考えの企業様は、専門家による無料相談をご活用ください。
SDGs視点での障がい者雇用の進め方【一覧表】
障がい者雇用を進める際には、SDGsの各目標と結びつけることで企業価値の向上にもつながります。
- 現状把握(自社診断)
障がい者雇用率、職場環境、教育制度などを調査し、課題を明確化する - SDGs目標との関連付け
目標8「働きがいも経済成長も」、目標10「人や国の不平等をなくそう」など、取り組みをどのSDGsに紐づけるか社内で共有する - 教育・研修の実施
障がい者への合理的配慮や発達障がいの理解に関する研修を導入し、従業員全体の意識を高める - 障がい者雇用に適している既存業務・新規業務を見える化
障がい者の特性に合わせてどのような業務を任せられそうか整理する - 職場環境の整備
バリアフリー化、ICTツール導入、在宅勤務の柔軟化など、実際の働きやすさを改善する - 就労支援・キャリア形成
支援サービスやジョブコーチを活用し、昇進・スキルアップの機会を保障する - 社外連携の活用
行政の助成金、教育機関、NPOとの協働により支援体制を強化する - モニタリングと改善
雇用実績や従業員満足度を定期的に評価し、PDCAサイクルで改善を続ける
また、SDGs考慮の考え方だけでなく、障がい者雇用に向けた業務切り出しの動き方を知りたい方は以下の記事もチェックしてみてください。
▶ 障がい者雇用の業務切り出し完全ガイド|6ステップ・事例・助成金・注意点を徹底解説
企業や自治体による障がい者への取り組み例(日本・世界)
障がい者雇用の推進は、個々の企業努力に加え、官民連携や国際的な取り組みとして進展しています。ここでは、日本と世界の代表的な事例を紹介します。
【日本】富士電機(製造業)の例|障がい者雇用促進
富士電機は、特例子会社「富士電機フロンティア」を設立し、障がい者が安定して働ける環境を提供しています。
設立の背景には「親亡き後も子どもが自立できるように」という切実な声がありました。現在は一人ひとりの特性に応じた業務を整備し、成長や達成感を重視した支援を実施。「働きがいも経済成長も」のSDGs目標に貢献し、誰もが活躍できる社会を目指しています。
(出典:富士電機「障がい者雇用の取り組み – SDGs貢献事例」)
【日本】リコージャパン(IT業)の例|活躍の場の提供
リコージャパンは、障がい者雇用を「社会貢献」ではなく人材確保や組織活性化の観点で推進しています。
業務を工夫して特性を活かすことで戦力化を実現し、社員全体のコミュニケーションや生産性向上にもつなげています。こうした取組みは目標8「働きがいも経済成長も」、目標10「人や国の不平等をなくそう」の実現にもつながっており、誰もが働きやすい環境づくりのモデルとなっています。
(出典:リコージャパン「リコージャパンSDGsの取組み:リコージャパンの障がい者雇用について 」)
【日本】SONYの例|ダイバーシティ推進・インクルーシブ実現
SONYは2022年度から障がい者や高齢者を製品開発プロセスに参加させ、2025年度までに全主要商品へ配慮を反映する方針を規則化しました。
リモコンに文字を併記する、ボタンに凸をつけるなどユニバーサルデザインを徹底し、誰もが使いやすい製品づくりを推進。SDGsの理念「誰一人取り残さない」を体現する取り組みであり、ダイバーシティとインクルージョンの実現に大きく貢献しています。
(出典:SONY「サステナビリティレポート2025」)
【世界】アメリカの例|合理的配慮と豊富な支援
アメリカでは、ADA法(障がいをもつアメリカ人法)にもとづき、障がいのある人を幅広く定義し、連邦政府で12%、請負業者で7%の雇用目標を設定しました。
合理的配慮の提供が義務化され、ジョブコーチや職業リハビリ機関による支援も整備されています。また、税制優遇や助成金、Disability Equality Index(DEI)による企業評価も導入され、雇用の質向上を重視する仕組みが確立されています。
(出典:厚生労働省「諸外国の障害者雇用促進制度について」)
障がい者とSDGsに関係についてよくある質問【FAQ】
SDGsで障がい者雇用が関わる目標は何番?
障がい者雇用は、以下に示す6つの目標との関係が深いです。
- 目標1 貧困をなくそう
- 目標3 すべての人に健康と福祉を
- 目標4 質の高い教育をみんなに
- 目標8 働きがいも経済成長も
- 目標10 人や国の不平等をなくそう
- 目標17 パートナーシップで目標を達成しよう
誰もが安心して働ける社会づくりは、経済成長や不平等解消の基盤となります。
SDGsにおける障がい者支援にはどんな取り組みがある?
障がい者が学びや仕事、生活をしやすい環境づくりが、世界中で進められています。就労支援制度や合理的配慮の義務化なども国ごとに推進されています。
職場や社会のバリアフリー化はSDGsのどの目標と関係する?
主に「目標8 働きがいも経済成長も」「目標10 人や国の不平等をなくそう」と関わります。誰もが働きやすい社内環境を整えることで、包摂的な社会の実現につながります。
まとめ|障がい者雇用はSDGsにつながる持続可能な社会への投資
障がい者雇用は、単なる法令遵守やCSR活動にとどまらず、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現に直結します。
つまり、障がい者雇用はコストではなく、企業と社会の両方の未来を豊かにする「投資」です。SDGsの視点を取り入れた雇用施策を進めることで、持続可能な社会と企業成長の両立を実現できるようになるでしょう。
障がい者雇用は「コスト」ではなく「未来への投資」です。
監修
鈴木 勇(スズキ イサム)
株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー
1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。
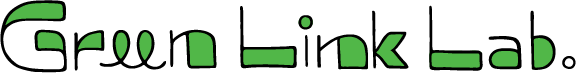
 無料オンライン相談
無料オンライン相談
