【2025年版】障がいの種類と特性別の特徴・配慮事例|合理的配慮の義務化・職場での具体例・雇用のポイントまで解説
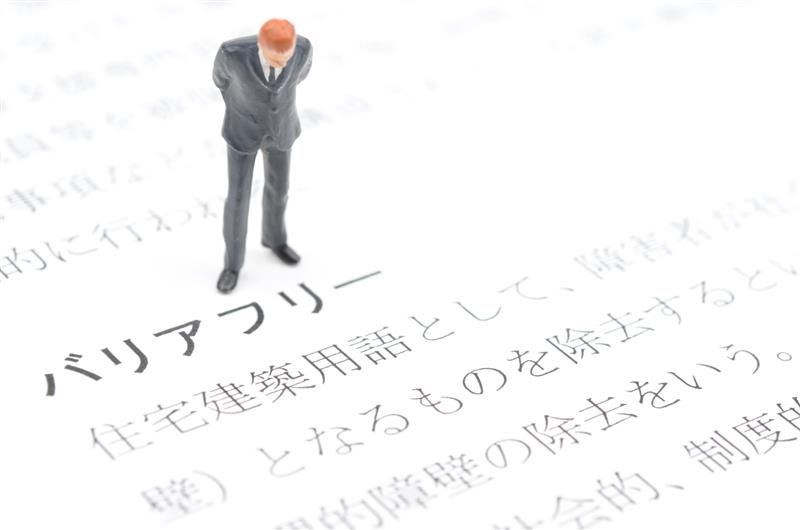
「障がい者を雇用したいけれど、どのような配慮が必要なの?」
「障がいの種類によって配慮は分けるべき?」
など、障がい者雇用における「合理的配慮」についてお悩みではないでしょうか。
この記事では、身体・知的・精神・発達障がいといった区分別の特徴や具体的な配慮事例を、国が公開している情報などをもとに解説します。
職場で実践できる合理的配慮のポイントや導入プロセスがわからないとお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
採用はできる。
でも“定着”に困っていませんか?
採用しても定着しない… そんな課題を抱える企業は少なくありません。グリーンリンクラボでは、独自のアセスメントを用いた質の高い人材紹介と、入社後も継続して行う定着支援・能力開発によって、働き続けられる環境づくりをサポートしています。
目次
企業が障がい者の「種類」「特性」を理解すべき理由とは?
企業が障がい者の種類や特性を理解すべきなのは、単に法律遵守のためだけではありません。
結論として障がい者の理解は、採用後の定着率向上や職場全体の心理的安全性の確保につながる重要な要素です。さらに、正しく配慮することで離職率の低下や生産性の向上にも直結します。
ここでは企業が障がい者のことを理解する理由を大きく2点に分けて解説します。
【理由1】障害者差別解消法と合理的配慮が義務化
改正障害者差別解消法により、2024年4月から合理的配慮の提供が全事業者に義務付けられ、障がいのある人への理解と支援は企業にとって避けて通れないテーマとなりました。
(出典:内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」)
(出典:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト「改正障害者差別解消法」)
合理的配慮とは、次のように障がいのある人が、障がいのない人と同じように人権や社会サービスを享受できるよう、個々の状況に合わせて行われる配慮のことです。
- 音声案内を文字化する
- 業務手順を図解で提示する
従来は行政機関における法的義務、企業における努力義務となっていましたが、この改正で企業規模に関係なく法的義務が課せられます。法令違反は行政指導や企業のイメージダウンにつながるため、事業規模を問わず必ず対応が求められます。
【理由2】企業の責務として「法定雇用率」の確保が重要
各企業には、障がい者の雇用における法定雇用率が定められています。
2025年時点は2.5%を確保する必要があるのに対し、2026年7月以降は2.7%へと上乗せされる予定です。
(出典:厚生労働省「事業主の方へ」)
なお、法定雇用率の未達はペナルティや社会的評価の低下につながるため、種類ごとの特性理解は欠かせません。特に、雇用率未達成の場合は納付金(1人当たり月5万円)の支払いが発生し、採用難のなかで企業ブランドにも影響します。
(出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」)
リスクを回避するためにも、種類ごとの合理的配慮を知り、職務設計に組み込むことが欠かせません。
また、障がい者雇用の基礎や仕組みから知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
加えて、障がい者雇用に関する法律を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
▶人事担当者が知っておきたい障がい者雇用に関する法律について
障がいの主な種類別|特徴と合理的配慮の事例一覧
障がい者雇用を成功させるためには、種類ごとの特性を理解し、それに応じた合理的配慮を講じることが欠かせません。
そして企業が理解しなければならないのが、身体・知的・精神・発達障がいなど、それぞれに異なる課題や強みが存在する点です。
| 障がいの特徴 | 傾向と配慮 |
| 身体障がい | 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障がいなど、物理的制約が中心 |
| 知的障がい | 理解や記憶の特性に応じたわかりやすい指示と繰り返し学習が効果的 |
| 精神障がい | 気分の変動や集中力の波に合わせた柔軟な勤務調整が不可欠 |
| 発達障がい | ASD・ADHD・LDなどで、得意と不得意の差や感覚過敏、注意力の特性に合わせた業務設計が求められる |
ここでは、厚生労働省が公開している合理的配慮の指針や事例集等の情報をもとに、障がいの特徴に分けた配慮例をわかりやすく解説します。
(参考:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」 / 「合理的配慮指針事例集【第五版】」 / 「障害者への合理的配慮好事例集(令和6年3月)」)
【グリーンリンクラボ担当者コメント】
合理的配慮は「特別扱い」ではなく、誰もが安心して働ける環境づくりの延長線上にあります。配慮の仕組みを整えることは、障がいの有無に関わらず全従業員の業務改善にも直結します。結果として離職率の低下や生産性向上につながるため、組織全体のメリットと捉えて取り組むことが大切です。
身体障がい(視覚・聴覚・肢体など)の特徴と合理的配慮事例
身体障がいは、視覚・聴覚・肢体不自由・内部がいなどに分類され、それぞれ職場で必要となる合理的配慮が異なります。
共通点は「環境を整えれば能力を十分に発揮できる」という点です。
以下より、各身体障がいの特徴別に合理的配慮の事例と企業の対応を紹介します。
視覚障がいへの配慮例
視覚障がいには、全盲から弱視まで幅広い特性があります。職場での合理的配慮としては、視認性を補う仕組みやICTツールの導入が不可欠であり、次のように「情報を視覚以外の方法で確実に届ける」ことが重要です。
- 音声読み上げソフトを導入する
- 点字資料や拡大文字を提供して会議資料・マニュアルの読み取りを補助する
- 社内レイアウトを整備して通路に障がい物を置かず、安全な移動を確保する
実際、保育士の職場では「絵本に点字シールを張り付けて読み聞かせができるように配慮する」、福祉系の職場では「業務の指示文書、職場内での回覧文書等を、周りの社員が読み上げて説明する」といった事例も見受けられます。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.8~9)
聴覚障がいへの配慮例
聴覚障がいは「音がまったく聞こえないケース」から「小さな声や特定の音域が聞き取りにくいケース」まで幅があります。そのため、職場での合理的配慮は次のように「情報伝達の方法を多様化する」ことが重要です。
- 手話通訳や要約筆記を導入し、会議や研修での意思疎通を円滑化する
- 口頭説明を補完し、聞き漏れを防止する
- 火災報知器を光で知らせる装置を設置する
実際、会議の際に手話通訳者の同席を認める職場や、スマートフォン等に聴覚障がい者向けの専用のアプリケーションをインストールしてやりとりを行う、といった企業事例もあります。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.20)
肢体不自由への配慮例
肢体不自由は、上肢・下肢の運動機能に制限がある状態を指すことから、歩行・立位・細かい動作などに困難を伴うことがあります。そのため次のような「環境整備」「補助機器の導入」が合理的配慮に欠かせません。
- 段差解消スロープ・エレベーターを設置する(バリアフリー環境)
- 高さを変えられる机、肘掛け付きの椅子を導入する
- 出勤や会議開始時間に余裕を持たせる
たとえば採用前には、入り口から近い場所を面接場所にすることで、面接場所への移動の負担を軽減するといった取り組みをしている企業もあります。
また、採用後は不必要なパーテーション等を取り除く、ゴミ箱を集約して床に置くものを最小限にするなど、移動のために十分なスペースを確保する配慮事例も見受けられました。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.26~29)
内部障がいへの配慮例
内部障がいとは、心臓・腎臓・呼吸器など体の内部機能に起因する障がいを指し、外見から分かりにくいのが特徴です。そのため、企業ではヒアリングを通じ、「通院・服薬・体調の波に応じた柔軟な働き方」を提供することが合理的配慮につながります。
- 定期的な通院が必要なため、休暇や時短勤務を認める
- 疲れやすさに応じて負担の少ない作業を割り当てる
- トイレに近い席や、空調の調整などを行う
実際、製造業では3交代制の業務を日勤に固定したり、データ入力業務で1時間に10分の休憩を確保したりと、内部障がいをもつ方が休憩を取りやすい環境を整えている事例が見受けられました。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.40)
知的障がい(軽度~重度)の特徴と合理的配慮事例
知的障がいは、知的発達に遅れがあるため学習や社会生活に支援が必要な状態を指します。
なお、知的障がい者は以下に示すA・Bの区分で判断をします。
- A判定の場合
重度・最重度とされており、日常生活で多くの援助が必要で食事や着替え、入浴などにも常時介助や支援が必要な人が多く、実際に一般企業で働いている人はほとんどいないのが現状 - B判定の場合
日常生活はほぼ自立しているものの、金銭管理や買い物、公共交通機関等の利用などに制限がある場合がある状況。作業内容や職場環境の調整や配慮によって一般企業で働ける
B判定の方のなかで、「職業的重度」と判定された方は雇用対策上の「重度」としてダブルカウント(2人)とカウントされます(身体障がい者手帳1級と2級の取り扱いと同じ)。「職業的重度」と判定されるには障がい者職業センタ-で「作業適性テスト」「日常生活スキル評価」等の評価結果を参考に手厚い支援が必要かどうかについて判定がされています。
厚生労働省の調査データによると、企業で働いている知的障害は職業的重度な方が11.8%、それ以外の方が81.0%の割合となっています。
(出典:厚生労働省「令和5年 障害者雇用実態調査」)
ここでは、知的障がいの症状の度合いを、症状が軽い人(軽度〜中度)、症状が重い人(重度)に分けて配慮事例や、企業が取り組みやすいアクションについて解説します。
症状が軽い人(軽度~中度)への配慮例
軽度〜中度の知的障がいのある方は、日常生活や基本的な業務をこなせますが、抽象的な理解や複雑な判断には困難があります。そのため企業では、視覚的・段階的な指示を用いたサポートが効果的です。
- マニュアルを写真や図解入りで作成する
- 作業手順をひとつずつ提示し、同時に複数の指示は避ける
- OJTで「見て覚える」形式を活用し、習熟度に応じて業務を増やす
- ピアサポートとして同僚を指導役に配置する
また職場では、本人の混乱を避けるために指示や相談対応を行う者を限定している事例や、予め定量的な目標を定めておき目標を達成できれば業務量等を増やすといったルールを定めている事例もあります。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.46~48)
症状が重い人(職業的重度)への配慮例
重度の知的障がいでは、作業面や安全面への配慮が不可欠です。次のように無理なく遂行できるシンプルな業務を設計し、短時間勤務や頻繁な休憩を取り入れることが合理的配慮となります。
- 危険のない軽作業(シール貼り、簡易清掃など)を担当してもらう
- 作業時間を短縮し、こまめに休憩を挟む
- 本人の得意動作(繰り返し作業など)を活かした役割分担にする
- 指導は「視覚化」と「繰り返し」を徹底する
たとえば、福祉施設の清掃の仕事では「モチベーションを維持するため、時間単位で作業内容を変更し、複数の作業を回しながら行わせる」という企業事例が見受けられました。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.48)
精神障がい(うつ病・統合失調症など)の特徴と合理的配慮事例
精神障がいには、うつ病・双極性障がい・統合失調症・不安障がいなど幅広い症状が含まれます。
厚生労働省のデータによると、25〜54歳で精神的な問題を抱えている方が多く、前職での雇用トラブルなどが影響しているケースもあるようです。
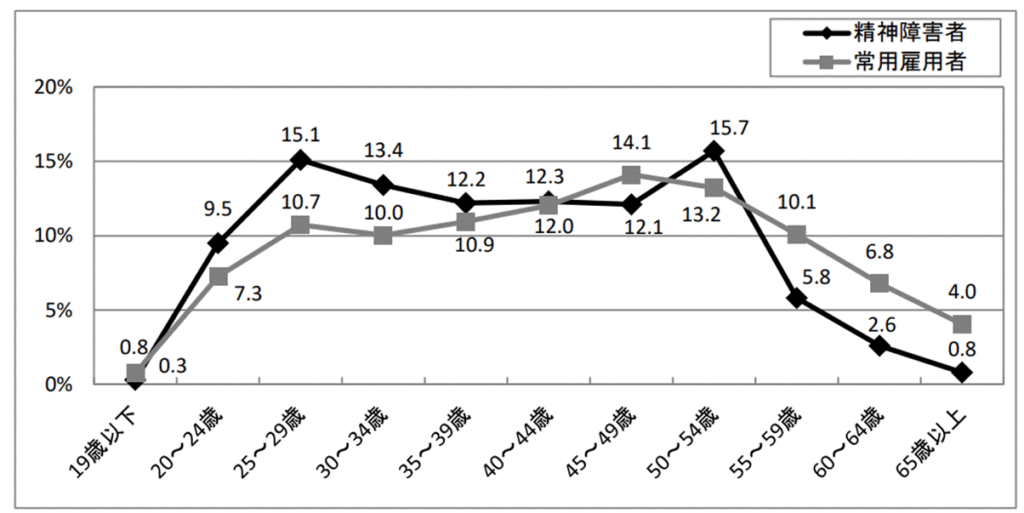
そのため、精神障がいのある方への合理的配慮は 「体調変動への柔軟対応」「職場環境の安心感」を軸に考えることが重要です。以下より、各障がいの配慮事例を紹介します。
うつ病・双極性障がいの配慮例
うつ病や双極性障がいのある方は、気分の波やエネルギー低下が特徴です。特に朝の不調や再発リスクが高いため、以下に示すような勤務時間や業務量の調整が求められます。
- 出退勤時間を柔軟化する(時差出勤・短時間勤務)
- 業務量を調整し、繁忙期は周囲でフォローする
- 定期的な面談を実施し、ストレスや体調を早期把握する
- 業務指示は「小さな単位」に分割し、達成感を得やすくする
事例としては、複数の者から指示すると本人が混乱するため、担当者のみが指導を行う、直接相談しにくい内容も相談できるよう相談用紙と投函する箱を設置する、といった配慮をする企業もあります。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.58)
統合失調症の配慮例
統合失調症は幻覚・妄想・注意集中の困難などを伴う疾患です。次のような合理的配慮で、安定した生活リズムを維持することが職場適応の鍵となります。
- 業務ルールを明文化し、あいまいさを排除する
- 定期的な休憩やリフレッシュ時間を確保する
- サポーターを配置し、不安時の相談相手を明確にする
- 医療機関との連携を保ち、服薬管理を尊重する
実際、就労支援機関や医療機関との連携を密にして、相談や体調が悪化したときの適切な支援につなげられるよう、会社外のサポート体制を構築している企業事例もあります。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.67)
障がい者雇用の支援に興味がある方は、以下の記事もチェックしてみてください。
▶【専門家による解説!】障がい者雇用支援サービス・支援機関の選び方は?
不安障がいの配慮例
不安障がいは強い不安や緊張から、出勤困難や業務遂行への支障をきたすことがあります。そのため、合理的配慮の基本は以下の「安心して働ける環境づくり」です。
- 在宅勤務やハイブリッド勤務を導入する
- 人前での発表や電話対応を避け、得意分野に業務を限定する
- 相談窓口やメンタルヘルス研修を整備する
- 突発的な不安発作に備え、休憩室や避難スペースを用意する
他の者にとっては些細なことであっても、本人にとっては大きな不安につながることがあるため、日々の疑問や困っていることには、丁寧に聞き取り答えるようにしている、といった事例もあります。
発達障がい(ASD・ADHD・LDなど)の特徴と合理的配慮事例
発達障がいは、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障がい(LD)など多様な特性を含みます。
合理的配慮の参考として、企業事例や発達障がいのある方に対する「見通しの明確化」「指示の具体化」「得意分野を活かす業務設計」 の3本柱の重要性を紹介します。
(参考:厚生労働省「合理的配慮指針事例集【第五版】」p.68~80)
自閉スペクトラム症(ASD)への配慮例
自閉スペクトラム症(ASD)のある方には「コミュニケーションの特性」「強いこだわり」「感覚過敏」などが見られます。そのため、次のようにあいまいな指示を避け、見える化した仕組みを整備しましょう。
- 業務手順をマニュアル化し、写真や図で提示する
- 会議では事前にアジェンダを配布し、発言順を決めておく
- あいまいな表現ではなく「○時までに△△を提出」と具体的に伝える
実際に、本人が混乱しないよう、ひとつの作業ごとにその担当からのみ指示を出すようにしている事例や、本人が慣れるまで障がい者就業・生活支援センターの職員による支援を活用するといった事例もあります。
注意欠如・多動症(ADHD)への配慮例
注意欠如・多動症(ADHD)のある方は、不注意や衝動性、多動性が特徴であることから、日常業務でのケアレスミスや時間管理のミスなどが起きやすい傾向です。そのため、合理的配慮としては次のような「集中しやすい環境づくり」と「スケジュール管理の支援」を徹底しましょう。
- タスクを細分化し、優先順位を明示する
- 業務の進捗を確認するチェックリストを導入する
- スマホやPCでアラーム・リマインダーを活用する
- デスク周りを整理し、集中を妨げる要素を減らす
企業によっては、障がい者が混乱しないように本人への作業指示を細分化し、ひとつの作業が終わる都度、次の作業を指示するといった対応を取る企業事例もあります。
学習障がい(LD)への配慮例
LDは「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習領域に困難を伴う障がいです。外見ではわかりにくいため、次のような適切なツールの導入や業務の工夫が合理的配慮となります。
- 読み書きが苦手な人には、音声読み上げソフトや入力補助ツールを導入する
- 数字の計算が難しい人には、関数を組み込んだExcelテンプレートを提供する
- 会議資料や業務マニュアルは文字量を減らし、図解やアイコンを多用する
職場全体に定着する実践方法|配慮してもらえないと思われないために
企業が合理的配慮を導入しても、実際に現場で「形だけの対応」と受け取られてしまうと配慮が定着しません。そこで大切なのが、企業全体に「理解と実践の仕組み」を根付かせることです。
ここでは障がい者から「配慮してもらえない…」と思われないためにやるべき、合理的配慮の実践方法を解説します。
自社の配慮は“形だけ”になっていませんか?
合理的配慮を制度化しても、現場に浸透しないのはよくある課題です。グリーンリンクラボでは、定期的なアセスメントや社内研修、継続的なフォローアップを通じて、合理的配慮が現場で実践される仕組みづくりをサポートしています。
【方法1】配慮事項の社内共有とマニュアル化に取り組む
障がい者雇用における合理的配慮を継続するために、担当者任せにせずマニュアル化に取り組みましょう。
たとえば、障がいの特性ごとの配慮事項をチェックリスト化し、人事・現場双方で共有することで、合理的配慮の再現性が高まります。効率よく管理するためにも、クラウド管理や社内ポータルで共有する仕組みを整えましょう。
【方法2】従業員研修・啓発活動を実施する
配慮を根付かせるためには、従業員全体の理解が欠かせません。そのため、障がい特性や合理的配慮の意義を学ぶ研修を定期的に行い、現場での対応力を強化しましょう。
この記事で紹介した事例や専門家の講義を取り入れることで、形だけでなく実効性のある啓発につながります。
【方法3】相談窓口やフィードバック体制を運用する
合理的配慮を整備する際には、障がい者本人が困りごとを気軽に相談できる窓口を設置することが重要です。
たとえば、人事部や相談員だけでなく、匿名で意見を集める目安箱といった仕組みを取り入れることで声を拾いやすくなります。また、定期的にフィードバックを反映させることで信頼性が高まり、定着率向上にも直結します。
【方法4】配慮内容の定期的な見直しと改善に取り組む
障がいの特性や体調は、時間とともに変化するため、導入した配慮を「一度決めたら終わり」にせず、定期的に見直す仕組みを設けると安心です。
医師や支援機関と連携しながら改善を続けることで、働きやすさと企業の対応力の両方を高められます。
【方法5】配慮してほしいことの聞き込み・アンケートを取る
障がい者への合理的配慮に対応した職場にするために、障がい者本人や従業員への定期的な聞き込みやアンケートを実施しましょう。
たとえば、どの配慮が役立っているか、改善が必要かを直接聞き取ることで、形骸化を防げます。小さな声を拾い上げる姿勢が「配慮してもらえない」という不信感を防ぐ大きなポイントです。
行き過ぎた障がい者への配慮はNG
障がい者への合理的配慮は義務ですが、必要以上の特別扱いは逆に本人や組織に悪影響を及ぼします。
たとえば、次のような対応は、本人の自立心を削ぎ、職場の一体感も損なうかもしれません。
- 業務の大部分を免除する
- 周囲が過度に気を遣いすぎる
- 障がい者を優遇しすぎる
重要なのは「障がい者ができないこと」を補い、環境を調整し、能力を発揮できる場をつくることです。職務の本質を守りつつ、障がいの種類や特性に合わせた適切なサポートを提供しましょう。
【グリーンリンクラボ担当者コメント】
配慮をしすぎて「業務の本質」まで外してしまうと、本人の自立心や職場全体の一体感を損なう危険があります。合理的配慮は“できないことを補い、できることを伸ばす”ための仕組みです。適切なバランスを保つことこそが、長期的な雇用の安定と定着につながります。
失敗しない合理的配慮の提供プロセス(導入フロー)
合理的配慮を実効性ある形で職場に導入するためには、段階的なプロセスを理解し、失敗を回避することが欠かせません。一般的には、以下の流れで進めます。
- 現状把握(業務棚卸し)
- 業務の分析と分類
- 切り出し業務の選定
- 業務設計とマニュアル作成
- 試行と評価(トライアル導入)
- 定着と支援体制の整備
詳しく提供プロセスを知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
▶障がい者雇用の業務切り出し完全ガイド|6ステップ・事例・助成金・注意点を徹底解説
明日から動かせる
“貴社版”の実践サポート
一般的な6ステップは参考になりますが、実際の現場に落とし込むには業務棚卸や評価指標の工夫が欠かせません。グリーンリンクラボでは、現状のヒアリングをもとに実践的な進め方を一緒に整理し、現場で動かせる形にサポートします。
障がい者の種類と合理的配慮についてよくある質問【FAQ】
配慮と特別扱いはどこまでを境界線とすべき?
合理的配慮は「過度な負担をかけずに本人が力を発揮できる環境を整える」ためのものです。本人だけに極端な優遇や免除を与えると特別扱いと受け止められる恐れがあります。業務上必要な支援に絞り、他の社員にも理解できるルールや仕組みとして導入することが、境界線を明確にするポイントです。
本人が配慮を希望しない場合の対応はどうすべき?
障がいのある社員が「特に配慮は不要」と伝えるケースもあります。その場合、無理に支援を押し付けるのではなく、基本的な安全配慮や体調確認は続けつつ、相談できる窓口やフォロー体制を整えておくことが重要です。本人が困った時に安心して声を上げられる仕組みを用意しておくことが合理的な対応になります。
雇用後に特性が判明した場合はどうすべき?
採用後に発達障がいや精神障がいなどの特性が判明することもあります。その場合は、まず本人の状況を丁寧にヒアリングし、医師や就労支援機関と連携して必要な配慮を整理することが大切です。いきなり業務を制限するのではなく、段階的に業務量や勤務形態を調整し、安心して働ける環境を整えることが求められます。
まとめ|特性理解と配慮が法定雇用率の向上につながる
障がい者雇用では、種類や特性を理解し、合理的配慮を職場全体で共有することが不可欠です。
無理のない支援体制を整えることで、社員一人ひとりが力を発揮でき、結果として定着率や生産性が高まります。特性理解と配慮は、法定雇用率の達成だけでなく、企業の持続的成長を支える基盤となるのです。
自社に合った配慮方法が分からない場合は、無料相談を活用してください。第三者の視点から計画や改善策の提案を受けることで、採用から定着まで安心して進められます。
定着で悩む前に、“設計”を見直しませんか?
【無料】
採用しても長続きしない——そんな課題を防ぐには、雇用設計と定着支援の両立が欠かせません。グリーンリンクラボでは、独自のアセスメントを活用した人材紹介と、入社後も続く定着支援・能力開発により、現場に根づく雇用の仕組みづくりをサポートしています。
監修
鈴木 勇(スズキ イサム)
株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー
1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。
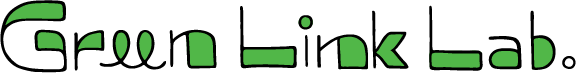
 無料オンライン相談
無料オンライン相談
